| Back to the menu |
 |
98/07/05 若人のための 日本映画入門 戦後黄金期編 |
| 出 演 |
音 楽 |
撮 影 |
脚 本 |
監 督 |
裸 の 島 | |||
| 田 中 伸 二 堀 本 正 紀 |
殿 山 泰 司 乙 羽 信 子 |
林 光 |
黒 田 清 巳 |
新 藤 兼 人 |
新 藤 兼 人 |
|||
| 昭 和 三 十 五 年 近 代 映 画 協 会 |
| 新藤兼人の実験 |
| モスクワ国際映画祭グランプリ受賞作品 |
| やっと「このひと」のことを書く番が廻って来た。お気づきだろうか、「出演」の欄に何回も何回も、同じ名前が登場していることを。『酔どれ天使』に始まり、『幕末太陽傳』『豚と軍艦』『キューポラのある街』等々、出演しまくっている俳優がいるのだ。「タイちゃん」こと殿山泰司である。 とにかく好き。どうしようもなく大好き。決して巧い役者ではない。セリフも動きも硬くて無骨。顔は...二枚目なんて夢のまた夢、30歳ごろから若ハゲで、一言でいえば「海ボウズ」だ。でもみんなタイちゃんが大好きだった。映画ファンはタイちゃんがスクリーンに登場すると思わずニヤニヤしてしまったし、なによりも監督たちに愛された。大島渚監督は「彼のいることでその映画のグレードが上がる」と言い、新藤兼人監督は「タイちゃんが出ると雰囲気が本当らしくなる...それが取り柄で、全てです」と熱く語る。 昭和14年のデビュー以来出演作品は実に400本以上、そのほとんどが脇役だったけれど、ちょっとだけ、タイちゃんが主役を張った作品群がある。前述の新藤兼人監督の独立プロ作品だ。タイちゃんを主役に...脇役一筋で歩んで来たタイちゃんを主役に、しかも主な登場人物が2人しかいない実験的な映画『裸の島』(35年)で、という新藤監督の狙いは前述の通り「リアリティの追求」にあった。 瀬戸内海の小さな島、川も井戸もないこの島で、畑を耕して暮らす一組の夫婦(殿山泰司、乙羽信子)。隣の島まで伝馬船を漕いで渡り、水を汲み、その水を切り立った段々畑に撒く。日々の生活はこれだけ、一日数往復、来る日も来る日もこの繰り返しだ。その寡黙な生活を描くために、この映画には一言もセリフがない。 この島の住人は4人だけ、夫婦とその子供二人である。それにいくらかの山羊や鶏もいる。上の子は小学生で、母親の漕ぐ伝馬船に乗り、隣の島の小学校まで通っている。山の中腹にある家の庭で、海を望みながら囲む食卓は豊かとは言えないが、家族の絆と慎ましやかな幸福を感じさせる。寡黙で無骨な父親だが、幼い子供たちが力を合わせて大魚を釣り上げた時は、でかしたとばかりに笑いながら子供をあやすのだった。 只、ひたすら、裸の島が映っているというわけではない。釣った大魚を対岸にある尾道の街まで家族4人で売りに行く場面もある。そこには店もあり、テレビもあった。ブラウン管の中で奇妙なダンスを踊る外人女性。そんな文明との対比も面白い。島の光景に圧倒されるが、昭和35年、1960年の物語でもあるのだ。一家は食堂で洋食を食べて、ロープウェイで千光寺公園に登る。束の間の観光であった(前述の『東京物語』同様、またしてもウチの田舎が舞台である)。そしてここでもセリフはない。 ある日、上の子供が急病になる。伝馬船を漕いで、医師を連れて来る夫。しかし...手遅れだった。ポンポン船が島に着き、小学校の教師と僧侶、同級生たちが上陸する。彼らが見守る中、幼い長男の亡骸は、両親の手によって、島の頂に埋められた。 翌日、天秤桶を投げ出し、畑の作物をむしって泣き崩れる妻。しかしいつもと同じく無言で働く夫を見て、また作業に戻って行くのだった。こうした事件の間も、終始、無言。寄せてはかえす波の様な、林光の主題曲が流れるのみである。 こんな映画に新藤監督はタイちゃんの持つ「本当らしさ」で挑戦した(女優の熊谷真美はこの映画を観て「ドキュメンタリーなのかと錯覚した」とか)。そしてそれは大成功を収めた。昭和36年、モスクワ国際映画祭グランプリに輝いたのだ。翌37年、新藤監督は『人間』で再び主役に起用。この作品でタイちゃんは同年の毎日映画コンクール男優主演賞を受賞した。 |
 |
『裸の島』 PV-1051 パステル・ビデオ (廃盤) |
| 松竹を飛び出して独立資本で映画製作を続けた新藤監督、今ではめずらしくないスタイルだが、これらの作品はそうした「独立プロ作品」の先駆けとなるものでもあった。そしてその盟友が、名優にして怪優のタイちゃんなのだった。 こうした栄冠を期に以降は次々と主役をこなし...とならなかったところがタイちゃんらしいや。三文役者を自称するタイちゃんは、再び脇役人生に戻り、平成元年の逝去までバイプレーヤーに徹し続けた。 「何でそんなにタイちゃんが好きなんだ?」−それは私がこのホームページでやっていることを、既に何十年も前にやっていたのがタイちゃんだからだ。 タイちゃんはジャズに詳しい。私の5億倍くらい詳しい。夜な夜なジャズクラブやホールに出没し、内外のジャズメンを聴きまくっていた。雑誌『スウィング・ジャーナル』などでライターとしても大活躍していたのだ。しかも西○ひかるちゃんみたいなチョーチン記事「ハリー・コー○ック・Jrにカンゲキしちゃいました!!」ではない。お気に入りは本格フリー・ジャズ、そして「オレの胸をおどらせてはくれなかったなァ」とか、「どうにもこうにも優雅で、オレにとっては上品すぎるジャズ・コンサートであった」といった絶妙の言い廻しで、「悪いモノは悪い」とハッキリ書いていたのだ。そんな俳優が今いるかい? |
| 殿山泰司氏 |
 |
| タイちゃんはなにしろ映画好きだ。映画に関する著作も多い。職業俳優の枠を飛び越えて、その文章からは映画と、映画人に対する愛情が溢れ出している。しかも、まさに「その場」にいたわけだから、正確でかつ面白い。私はいわゆる「映画史」のたぐいは読んだことはなくて、日本映画の歩みってヤツを、実はタイちゃんの名著『三文役者あなあきい伝』(ちくま文庫)で学んだのだ。 そしてタイちゃんは何よりも名文章家であった。読書家としても有名で、ミステリー小説に詳しく、その読書量は評論家も逃げ出すほど...実は撮影の待ち時間に読んでいたらしいのだが。自らの書く文章はそのミステリーの様に高尚...ではなく、極めてワイルド。ジャズ・ピアニストにして名エッセイストの山下洋輔氏、直木賞候補にもなったパンク歌手、町田康氏もその影響を公言している。エッセイは今でも入手可能。あの文章が実にクセになるのだ。 ああ、それにしても、一回でいいからタイちゃんと呑んでみたかったなァ。作家の村上龍氏は浅草の酒場で遭遇、挨拶も程々にフリー・ジャズの話で盛り上がったそうだ。いいなァ。私だったらまずジャズ、それから邦画の監督や、俳優の話、そして...。 ともあれ、日本映画、モダン・ジャズ、ミステリー小説から「わが敬愛する川島旦那」−川島雄三監督に対するこだわりまで。私なんか、タイちゃんのケツを追いかけているだけって気がするなァ。男のケツなんか追いかけるナッ!!バカッ!!それともカマかい?イヒヒヒ...。 ...まずい、「殿山文体」になってしまった。ともかくそんなタイちゃんの名演を是非観て欲しいと思う。殿山泰司、平成元年死去。昭和が終わったあの年に、タイちゃんの映画人生も、そっと幕を降ろした...。 |
| タイちゃん大ニュース! |
新藤兼人監督が殿山泰司をモデルとした映画『三文役者の死』(仮題)の製作を決定。新藤監督が記した岩波書店からの同名の評伝の映画化で、主役は竹中直人の模様。くわしくはこちらかこちらで。タイちゃん、映画になる。 |
| この『裸の島』はビデオ、レーザー共に廃盤です |
| 出 演 |
音 楽 |
撮 影 |
脚 本 |
原 案 |
監 督 |
馬 鹿 が 戦 車 で | |||||
| 松 村 達 雄 谷 啓 他 |
岩 下 志 麻 花 沢 徳 衛 東 野 英 治 郎 |
ハ ナ 肇 犬 塚 弘 飯 田 蝶 子 |
團 伊 玖 磨 |
高 羽 哲 夫 |
山 田 洋 次 |
團 伊 玖 磨 |
山 田 洋 次 |
や っ て 来 る | |||
| 昭 和 三 十 九 年 松 竹 |
| 山田洋次の前衛 |
| 何だ?この、前衛は!! |
| 最後はこの作品、山田洋次監督の『馬鹿が戦車(タンク)でやって来る』(昭和39年・松竹)である。数ある邦画の中でも、特筆すべき「奇作」であると言える。解釈はある部分、皆さんにお任せしたいとも思う。ストーリーを、じっくり書く。 オープニングは3人乗りの釣り舟である。釣果の振るわない釣客の課長(松村達雄)と部下(谷啓)に、船頭(東野英治郎)が「タンク根(ね)に行ってみようか」と切り出す。「タンク根?戦車隊が捨てたのかい?」と聞く松村に、船頭は「いンや、違う。あれは...」と昔話を語り始める。 舞台は「日永(ひなが)」という山間の小さな村である。この日永、怠け者が多く、暇さえあれば人の噂話ばかり、「日永から嫁取るな」とまで言われる程の、日本の「ムラ」を凝縮した様な処である。そしてその中でも困りモノとされているのが村外れに住む貧乏な親子であった。家族は3人、耳の遠いバアサマ(飯田蝶子)、少年戦車兵帰りの長男・サブロウ(ハナ肇)、そして自分を鳥だと思っている知恵足らずの次男・ヘイロク(犬塚浩)である(ん、名前と家族構成が合わないな。ま、いいか)。 家長のジイサマは既に亡く、気の荒いサブロウを中心に、ツンボのバアサマと、キチガイのロク(差別しているわけではない。劇中でこう言われているのだ)、ものが無くなったり、不幸があったりする度に「あの家のせいぢゃ」と謂われのない差別を受けているのだった。 サブロウ一家は村の地主、立花仁右衛門(花沢徳衛)から譲り受けたわずかばかりの畑を耕して暮らしている。元は仁右衛門の小作人であったのだ。農地解放とはいうものの、かつての上下関係が残り、未だにこの二軒はしっくり行かない。サブロウが住む納屋には「トラクター修理」の手書き看板もあるが、こちらは商売にはなっていない様子だ(サブロウが機械に強く、手先が器用である、ということを覚えておこう)。 そんなある日、長らく病床に臥していた仁左衛門の一人娘、のり子(岩下志麻)の床上げ(快気祝い)が催される。おりからの秋祭りと重なり、村はおめでたい雰囲気で一杯だ。 「起きられるようになったら、真っ先にこの家に謝りに来ようと思っていたの」、前日、のり子はサブロウ一家を尋ねて日頃の仁左衛門の不合を詫びていた。「サブちゃんも床上げには来てね」。 村一軒の床屋で整髪し、一張羅の背広を着たサブロウは村人に笑われながらも仁左衛門の屋敷に向かう。しかし、身分の違いをさんざん馬鹿にされた上に、勝手について来た弟・ヘイロクの奇態を笑われ激怒。大暴れの末、留置場に放り込まれてしまう。そしてサブロウの保釈を巡って村会議員(菅井一郎)がモウロクしたバアサマから財産の畑を巻き上げてしまうのだった(床上げからの帰り道にヘイロク役・犬塚のアップが映る。目が完全にイッている。凄い。またこの頃の犬塚は昨年急逝した名優、趙方豪にそっくりであることにも気づく)。 サブロウが家に戻り、数カ月、不気味な沈黙。そしてある日、突然、キレる。鉄の煙突の飛び出したサブロウの住む納屋は、実は戦車小屋だったのだ。復員の時に盗み出した戦車「愛国87号」で、サブロウは「ムラ」を破壊しまくる。仁左衛門の家、村会議員の家...壁を突き破り、屋敷を潰す! 一旦サブロウが家に帰った隙に、村人達は対策を講ずる。しかしその時、火の見櫓の上で両手をばたつかせていたヘイロクが転落、哀れ命を落とす。「お前らがロクを殺したんだ」と、サブロウが再び暴れ出す。しかし心から悲しむのり子の姿を見て我に返り、老母とふたりロクの亡骸(なきがら)を黙々と運ぶのだった。 後味の良くない村人たち、どの家もしんみりとしている。その晩、村の通りを戦車が音をたてて通り過ぎて行く。 翌日、村人の代表(常田富士夫ほか)と駐在(穂積隆信)が戦車の轍を追いかける。2本の轍は、畑を越え、山を越え、海沿いの隣町「北浜」に向かっていた。戦車は夜半に、かつてのり子が入院していた診療所に立ち寄ったらしい。医師(高橋幸治)は「サブロウがロクちゃんを連れて来た。気の毒だけどもう死んでいたよ。死体は引き取れないというと黙って戦車に戻って海の方に向かった」と言った。彼らが海に向かうと...轍は波打ち際に消えていた。海にに向かって、一直線に...。 沖合を見つめて呆然と立ち尽くす村人3人、少し手前で四つんばいになって力尽きる駐在、このラストシーンには息をのむ。『ストレンジャー・ザン・パラダイス』('84年・米=西独)の様でもあり、『ブリキの太鼓』('79年・西独=仏)の様でもあり...ここで観客は自分が観ていた、笑って来た映画が実は「喜劇」ではなかった事に気づく。 さてどうだろう?異常に詳しくストーリーを紹介してしまった。しかし、紹介したかった。これは喜劇の枠を借りた、ヌーヴェルヴァーグ、あるいは実験映画の様にも思われる。不思議な場所に位置する作品だが、間違いなく名作、だと思う。 この映画、ここ10年で2回TV放映されている。しかし「キチガイ」や「ツンボ」やモロモロの放送禁止用語が全部カットされてズタズタになってしまうのだ。せめてヴィデオで、いや、このラストシーンを考えるとやはり映画館のスクリーンで観て欲しい。注意をしていると「山田洋次特集」などで結構頻繁にやっている。 |
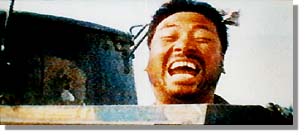
ハナ肇のサブロウ
| 山田洋次監督−「松竹大船調」といわれるホームコメディの伝統をお馴染み『男はつらいよ』シリーズで現代に継承、昇華させた人物である。しかし、本当は、こういう映画を作る人だったのだ。かつて私はジャズ・コーナーで「前衛が出来るピアニストのスタンダード、歌伴は素晴らしい」と書いた。思うに山田洋次という人は本来はかなり前衛的な人物で、すべて計算の上でポピュラリティーの高い『男はつらいよ』を撮っていたのではないだろうか。「前衛の出来る監督のスタンダード」である。 シリアスに撮った『家族』(昭和45年・松竹)も名作であった。炭鉱離職者の一家が長崎から、遠く北海道を目指す。途中大阪で急病になった赤ん坊に狼狽する父(井川比左志)の必死の形相、北海道に着きそっと息を引き取る老父(笠智衆)、観てから20年以上経とうというのに、あの70年代的なザラっとした「光線」は忘れることが出来ない(小学校の時に親と一緒に逗子市立図書館ホールの自主上映会で観た。古過ぎて細部自信ナシ)。 だが、『家族』が語られるならば、この『馬鹿が戦車で...』も語り継がれなければいけない、と思う。日本的「ムラ」社会の因襲を訴える作品であることは容易に察しがつく、しかし、それだけではない。だが、それが何かは私には語れない。何だ?この、前衛は!!。 なお原案は作曲家の團伊玖磨氏、同時に音楽も担当している。フランス現代派の影響を強く感じる氏のスコアが、この作品を一段高いところに押し上げてもいる。最高のオリジナル曲、ほとんどラヴェルかドビッシーだ(サントラ欲しい!)。特にラスト・シークエンス、轍の追跡から海岸のシーンは圧巻であった。繰り返して言う、これは「喜劇」であって「喜劇」ではない。 最後に「このサブロウのキャラクターが車寅次郎−フーテンの寅の元になった」という監督の談を記しておこう。 |
| この『馬鹿が戦車で...』は松竹から廉価版ビデオが発売されています |

さてつぎは最後のページ
日本映画を観る方法と日本映画リンクです
上のテロップをクリックして下さい