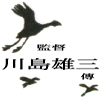 |
99/06/11 監督 川島雄三傳 『幕末太陽傳』 |
| 出 演 |
音 楽 |
撮 影 |
脚 本 |
監 督 |
幕 末 太 陽 傳 | ||||||
| 西 村 晃 熊 倉 一 雄 殿 山 泰 司 他 |
小 沢 昭 一 菅 井 き ん 芦 川 い づ み |
金 子 信 雄 山 岡 久 乃 岡 田 真 澄 |
石 原 裕 次 郎 二 谷 英 明 小 林 旭 |
フ ラ ン キ | 堺 南 田 洋 子 左 幸 子 |
黛 敏 郎 |
高 村 倉 太 郎 |
川 島 雄 三 今 村 昌 平 田 中 啓 一 |
川 島 雄 三 |
|||
| 昭 和 三 十 二 年 日 活 |
 |
川島日活最終作品にして代表作 |
|
| |
| 『幕末太陽傳』 製作背景 |
| この映画、日活のマークに続いて「製作再開三周年記念作品」というタイトルが出てくる。戦争による中断?まぁそうともいえるのだが、事情は単純ではない。 日活という映画会社は戦前から、いや古く大正時代から存在していた。創業は大正元年、実は大手では日本で最も長い歴史を持つ映画会社なのだ。ちなみに続く松竹がそのしばらく後、大正9年の創業である。 多摩川と京都にスタジオを持ち『忠治旅日記』(昭和2年)や『丹下左膳』(昭和8年)といった大河内伝次郎主演の時代劇の傑作や、『足にさわった女』(大正15年)の様なモダンな現代劇も残していた。伝説の天才監督、山中貞雄の現存する3本中の2本、『丹下左膳余話・百萬両の壺』(昭和10年)と『河内山宗俊』(昭和11年)、最近再評価の機運が高い和製オペレッタの傑作『鴛鴦歌合戦』(昭和14年/マキノ雅弘監督)も旧日活作品である。 ところが戦時中の昭和17年、企業整備令により新興キネマ、大都映画と強制的に合併させられ、「大映」となり一時その実態を亡くしてしまうのだ。これが戦中から戦後の一時期まで続いた日活の製作停止期である。そしてその背景には軍部によるフィルム供給の統制があったと云われる。 さて、国策会社かと思われた大映だが、どこからともなく現れた永田雅一なる怪人物の力もあり戦後も存続。黒澤の『羅生門』(昭和25年)や、溝口の『雨月物語』(昭和28年)などの傑作を世に送り出した。昭和46年に一度倒産するも、徳間書店グループの配下で会社自体は現存している。皆さん良くご存じの周防正行監督作品『シコふんじゃった』(平成4年)や『Shall We ダンス?』(平成9年)を製作したあの会社である。 敗戦から10年近く経ち、その大映から旧日活の製作陣が独立した。合併を免れ細々と輸入映画の配給などを行っていた配給部門と共に、昭和28年「日活株式会社」復活。復活に懸ける思いは非常に強く、東京都下調布市に作られた大撮影所は冷暖房完備(当時、松竹大船ですら吹きさらしだった)の上、最新、最高の設備を誇った。 最高だったのは設備だけではない。人材についても当時の最高を狙った。旧日活陣と、先行して移籍した者が中心となり「技術陣は東宝から、監督は松竹から」と引き抜きを行った。この川島雄三も松竹からそうして身を転じた移籍組なのだが...。 その様な映画人たちの「思い入れ」もあるであろう「記念作品」で、川島はいくつもの無茶をする。まったく、大変なことをしでかしてくれたのだ。 まずはテーマとタイトルの問題。日活はこの前年に『太陽の季節』(古川卓巳監督)と『狂った果実』(中平康監督)という作品を発表し大ヒットを記録していた。同時に「太陽族」なる人種までも生み出し、単なる映画を超え、新風俗ともいえる一大センセーションを巻き起こしていた...のだが、保守層からは非難を受けてもいたらしい。劇中に描かれた若者の無軌道な振る舞いが風紀上好ましくないというのだ。 のちの東京都知事サマがお書きになったもの(いずれも石原慎太郎原作である)がそんなにも反道徳的かは、まぁ「古い価値観ゆえのもの」とも思えるのだが、ともかく日活首脳陣は「太陽族はマズイ」と考えていた、にもかかわらず、川島自らが命名したタイトルは『幕末太陽傳』であった。 また「記念作品」が喜劇映画、しかも古典落語を繋ぎ合わせたものであるということも多少の波紋は投げかけていた様だ。まだ喜劇映画の地位が文芸映画よりも一段低かった時代でもある。しかしこれこそ川島の信念を表す部分で、喜劇で傑作を作り、その地位を上げようともしていた。そしてこの喜劇へのこだわりは生涯を通じて貫かれることになる。 更にそのキャスティングについてもそれなりの衝撃があったらしい。石原裕次郎や小林旭、二谷英明など当時の日活オールスターを配しているにもかかわらず、彼ら全員を脇に廻し、『東京バカ踊り』(昭和31年/日活)や『フランキーの宇宙人』(昭和32年/日活)といった怪作喜劇に出演していた元・ジャズドラマー、フランキー堺を主役に据えてしまったのだ。「マゲを結った太陽族」、「裕次郎初の時代劇」などと当時の新聞がこぞって書き立てたにもかかわず、である。 |
 |
撮影スナップ 二谷英明、川島雄三、 石原裕次郎、フランキー堺 |
| そして何よりも、製作費でモメた。これは日活側にも問題があり、撮影所長を筆頭に川島には「幾らかかってもいい」と言っておきながら、実際には2千3百万という具体的な上限を設定していた。つまり「二枚舌」を演じていた。そんな事情を察した川島は日活に対し強烈な不信感を抱き、この作品撮影中の撮影所との関係は決して円満なものではなかったという。逆に川島は撮影スタッフには「金はいくらかけても構わない」とブチ上げていた。あたかも劇中で「大舟に乗った気でいねィ」とカマしていた、佐平次の如く、である。 結果、この巨大なセットを用いた超本格的時代喜劇は3千万近い製作費を費やすことになったのだが、同時に「日本喜劇映画の金字塔」とまで称賛され、川島の代表作を超えて戦後日本映画の傑作とまで云われるものになった。そして川島はこの作品を最後に日活を去り、3社目にあたる東宝系の東京映画に移籍した。 しかしだ、川島は何故にここまで会社の意図にことごとく反して製作を行ったのか、そしてこの映画に漂う反骨と逃避の感触は何なのか...それはのちほど「解説−佐平次はどこまで川島だったか」にて。それでは前口上はここまでにして、本編を...。 |
 |
首が飛んでも動いてみせまさァ |
|
| |
| 『幕末太陽傳』 物語 |
| 文久二年暮れの品川宿。夜の街道筋で馬上のイギリス人と志道多聞(二谷英明)ら攘夷の若者達が一悶着起こしている。鉄砲で手を撃たれ懐中時計を落とす多聞。すかさず飛び出してそれを頂戴するのがこの映画の主人公、佐平次(フランキー堺)である。 『幕末太陽傳』のタイトルと共に画面は一転、現代(昭和32年当時)の品川へ。「東海道線の下り列車が品川駅を出るとすぐ...」という軽妙なナレーション(加藤武)と、デキシー風のテーマ音楽(アーヴィング・バーリンの「アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド」。音楽は黛敏郎)。「これから面白い映画が始まる!」という雰囲気がひしひしと伝わって来る。この『幕末..』の他、30年の日活作品『愛のお荷物』や、37年の東宝作品『箱根山』など、川島のオープニング・タイトルの軽妙さは本当に見事である。 スタッフ・ロールに重ねての品川紹介の最後に「さがみホテル」のネオンが映り、それがワイプして「相模屋」の行灯(あんどん)に変わる。時は再び文久へ。素晴らしい!。 さてその相模屋に件の佐平次が入ってくる。仲間3人を引き連れて「大舟に乗った気で居ねィ」と景気よくブチ挙げている(このシーンでの呑み込みの金坊(熊倉一雄)のおどけた芝居は絶品である)。芸者4人を上げて、夜を徹してのドンチャン騒ぎ。芸者の叩く太鼓のスティック...じゃなかった、バチを取り上げて自ら叩くフランキーが、ジーン・クルーパばりに右手でくるくるとバチを回す演出には思わずニヤリとさせられる。 翌日、ひとり残った佐平時、勘定書を持って来た店の若衆(岡田真澄、流れ女郎が捨てていったハーフの品川っ子という設定)に「一文も懐に持ってないってんだから面白いじゃねぇか」と開き直り、店に居残って働いて返す、ということになる。 |
 |
佐平次ご乱行 西村晃、フランキー堺 |
| しかしこれからの活躍ぶりが凄い。勘定をため込んだ高杉晋作(石原裕次郎)ら攘夷の志士からはそのカタを取って来る。女郎こはる(南田洋子)に入れ揚げた挙げ句、縁組の誓いを書いた起請文が衝突してしまった仏壇屋親子(殿山泰司、加藤博司)の前では、たった今自分で書いた起請文を懐から取り出し、出刃包丁片手に「やい、こはる!てめぇはよくもこの俺に!」と大芝居を打ってその場を収め、親父から小遣いまでせしめる始末。 どうやらこれは佐平次の計画的犯行で、海に近い品川宿に居残ってしばしの転地療養−サナトリウムの様なもの?−と決め込みたいようだ。 こんな佐平次を女郎衆が放っておく訳がない。板頭(いたがしら、一番人気のこと)を争うこはるとおそめ(左幸子)が「年(ねん)が明けたらわっちと所帯を」と言い寄るも「胸の病にゃ女は禁物」とはね返し、寝起きする行灯部屋で薬の調合に専念する。これは、実は、川島の姿なのである。 「生キル為ノ薬デス」と言いながら、一回に20錠以上、1日にその数倍もの薬を服用していた川島。自ら調べた薬を、行きつけの薬局で購入していたという。また一生妻をめとらず、同棲していた女性が妊娠した時も生むことを許さなかった。自分の持つの遺伝障害を自らの代で断ち切ろうとしていたのだ。 「へいへい、何でげしょう」とおどける佐平次が、行灯部屋に戻り独りになった瞬間に見せる鬼気せまる表情には思わず息を呑む。川島と今村昌平(脚本・助監督)が力を入れた演出なのだそうだ。しかしひとたび廊下から声が掛かると「へ〜い」を景気のいい声を上げて飛び出して行く。元の表情に戻って...。 二つの物語、相模屋の放蕩息子・徳三郎(梅野泰靖)と女中おひさ(芦川いづみ)、そして高杉晋作ら攘夷の志士達のエピソードを軸に終盤を迎える。おひさは父・大工長兵衛の借金のカタに働かされているのだが、結局払えずに遂に女郎として店に出されそうになる。「可哀相ダは惚れたってことよ」と気になる徳三郎。おひさも決断、二人は駆け落ちを企(くわだ)てる。 一方、高杉らは御殿山の英国公使館の焼き打ちを企(たくら)んでいるが、肝心の絵図面が手に入らない。この二組、頼るところは当然佐平次である。 さてここで名場面。あまりにチョロチョロし過ぎる佐平次を幕府のスパイではないかと疑った攘夷の志士たちが、佐平次を試す。高杉が代表となり焼き打ちの全容を打ち明け、更には切りつけんと迫りその出方を見ようというのだ。 そしてこの時の佐平次の態度が凄い。怯えるでなく、媚びるでなく、「へへえ、それが二本差しの理屈でござんすかい」と高杉に挑む。「ちょいと都合が悪けりゃ『こりゃ町人、命は貰った』と来やがら、どうせ旦那方は、百姓町人から絞り上げたおかみの金で、やれ攘夷の勤皇のと騒ぎ廻っていりゃ済むだろうが、こちとら町人はそうはいかねえ」「何ッ...?」「手前一人の才覚で世渡りするからにゃア、へへ、首が飛んでも、動いてみせまさア!」。佐平次一世一代の大啖呵、この映画の根幹を成す庶民のヴァイタイティを凝縮した名セリフである。 黒澤活劇との違いにお気づきになるだろうか。同じ時代劇でありながら、あちらは侍の目から見た庶民、町人の生きざま、川島時代劇はあくまで我々庶民の視線と心情を貫き通しているのだ。そしてこれは川島創作の根源ともいえる。詳しくは後ほど、「ロケ地探訪」の後半で。 |
| 品川沖の名場面 「首が飛んでも動いてみせまさァ」 |
 |
| 蔵の中に幽閉されていた徳三郎らを凝った方法で逃がし、おひさを利用して絵図面も入手(このへんは観てのお楽しみ)、二組を同じ船に乗せる。「お前さん方を逃がせば、オイラここには居らンねぇ身体だ。なぁに丁度潮時」、佐平次最後の大奮闘である。 宿に戻った佐平次、時はあたかも大引け(深夜営業の閉店時間)である。言い寄る女郎衆を後に、いよいよ逃げ出そうとしたその時、千葉の田舎親父・杢兵衛(市村俊幸)に掴まってすっかり調子を狂わせてしまう。「こはるサァ、どんな案配だァ」と聞く杢兵衛を「実はオッ死んじまったんでィ」とケムに巻くが、異常にしつこい杢兵衛に「寺ァどこだ、お参りするべェ」と付き纏わられる。 近くの墓場に連れて行き、適当に誤魔化そうとするがこれも不発。要領のいい筈の佐平次が、ここでは全くサッパリなのだ。「あっしなんか若こうござんすから、墓にはとんと縁がねぇもんで」という佐平次、「いンや、おめさっきから妙に悪い咳コイてるでねェか」と言われ暗い表情を見せる(咳のことを言われふっと暗くなるシーンは他にもある)。業を煮やして逃げ出す佐平次。杢兵衛の「地獄サ落ちっど〜!」の声を背に、全力疾走だ。「俺はまだまだ生きるんでぇ!」と叫びながら。そして、エンドマーク...。 |
 |
ラストシーン 逃げ出す佐平次 |
| 「面白いなぁ」と思うシーンが幾つもある。中でも印象深かったのはおひさが佐平次に駆け落ちの手助けを頼む場面。当然ロハでは引き受けない佐平次に大枚十両を払うという。「でも今すぐじゃないんです。毎年一両ずつ貯めて、十年経ったら返します」というおひさに、佐平次ひとこと「十年経ったら世の中も変わるぜ」...そう、世の中も変わる。六年後が明治維新、十年後は明治5年なのだ。 なお抱腹絶倒のエピソードはまだ山ほどある。書ききれないので思い切り省いたのだ。とにかく爆笑の連続(特に貸本屋の金造(小沢昭一)のシーケンス、クックック...)、111分があっと言う間だ。 |
 |
佐平次はどこまで川島だったか |
|
| |
| 『幕末太陽傳』 解説一 |
| 日活を辞める気、いや、潰す気で撮った作品なのだ。製作背景に書いた以外にも、当時川島と日活側はいくつもの問題で合わなくなって来ていた。結論から言えば川島のそうした心情の吐露がこの作品のある部分−反骨と逃避を形成した、とも云える。 まずは金銭面、松竹の二倍ともいわれる専属料、監督料で日活への移籍を決めた川島だが、移籍後の昇給に関して日活側は極めて冷たかった。これは川島に限らず、石原裕次郎の『嵐を呼ぶ男』などでドル箱監督となった井上梅次が昇給を申し入れた時も、時の堀久作社長は「切れ!」と言い放った位である。 日活時代の川島は生活も安定し、受けの良い佳作を次々に作り出していた。何よりもプログラム・ピクチャー中心で一種「御用監督」的存在だった松竹時代とは違い、その才気を発芽させ、「川島調」を確立したのはこの日活時代であったのだ。にもかかわらず、昇給はナシ。これでは面白いハズがない。 ここまではたまに語られていることだが、私はもうひとつの要因、「日活のアクション偏重を予見しての退社」という説が気になる。 昭和29年の製作再開から『警察日記』(昭和30年/久松静児監督)や『月は上りぬ』(昭和30年/田中絹代監督)など風情に満ちた文芸映画で好評を得ていた日活ではあるが、前述の『太陽の季節』などのヒットを期に若者向けのアクション映画路線へのシフトが静かに進行していた様なのだ。 結果それは一連の裕次郎映画や小林旭の『渡り鳥』シリーズ、『風来坊』シリーズを生み、昭和41、2年頃の鈴木清順監督作品群、更には同45年からの『野良猫ロック』シリーズにまで繋がることになるのだが、川島は日活のそうした流れを予見、その中に「自分の生きる道が見えない」と考えたらしい。 アクション映画の演出、これは病気が進行し体力を失い始めていた川島には難しいものだった。観念的な演出を得意とする川島には、やはり肉体的なパワーの時代−映画監督・渋谷実氏は「エネルギー主義の旋風が映画界を吹きまくった時代」と呼んでいる−のシャシンを撮ることは不可能だったのだろうか。強気だった川島が当時の助監督、浦山桐郎に吐いた数少ない弱音、「俺は体力がネエカラナア...」が辛く、響く。 比較的自由に芝居をさせる川島が、佐平次役のフランキーには執拗に駄目を出し続けていたという。三階建ての相模屋を風の様に駆け回る、全能の怪人佐平次を、不自由な体で歩行もままならない己の分身と捉え、託して...のことだったのだろうか。 |
 |
撮影スナップ 川島とフランキー、左幸子 後方に浦山桐郎、今村昌平ら |
| ともあれ背景で書いた川島のゲリラ的、テロリスト的、クーデター的撮影の裏にはこの様な事情があったのだ。 しかしまぁ、人間不思議なもので「やるだけやって逃げちまえ!」と思うと大傑作が出来たりするのだな(笑)。 さてここまで読むと川島と佐平次がダブリ始めては来ないだろうか?川島はこの映画の主題をフランキー堺に向かって「アノ、それ、積極的な、逃避精神...」とぼそっと語ったという。その言葉は佐平次に対してであり、同時に自分に向けられたものでもあったのだろう。 しかし逸話は更に続く。次に有名な「幻のラストシーン」について。 |
 |
ラストシーン考察 昭和32年のヌーヴェルヴァーグ? |
|
| |
| 『幕末太陽傳』 解説二 |
| 撮影も押し詰まったある日のこと、川島は突如、台本の変更を言い出した。田舎親父の杢兵衛大尽(市村俊幸)に捕まった佐平次が海沿いの寺から走って逃げ出すが、これをさらに引き延ばし、撮影所の出口から飛び出して現代の−昭和32年の−東京の町に投げ出そうというのだ。 スタッフ、キャストは猛反対。今聞くとなかなか面白い演出なのだが、何しろ今から40年以上も昔のこと。あまりにも斬新過ぎるそのアイデアは通らず、助監督・浦山桐郎から頼まれたフランキー堺が川島を説得、川島が折れて結局は幻と終わった。 この演出について、出演者のひとりである小沢昭一氏が雑誌のインタヴューで詳細に語っていた。それによると佐平次の出現する先は昭和32年の北品川カフェー街、佐平次だけが映画そのままの江戸時代の装束で、他の出演者、左幸子や南田洋子は赤線地帯の売娼の姿、小沢昭一は自転車に乗った貸本屋の姿でそれを見る、というものだったらしい(ちなみに小沢氏は「絶対にその方がいい」という数少ない肯定派であった)。 実に残念である。確かに当時の映画界の常識ではスクリーン上の世界は強固なもので、その裏を見せる、その世界を壊すというのは掟破りのことだったのだろう。フランキーの説得の弁、「いきなり現代の、それもスタジオの中をバラすのは、折角そこまで積み重ねて来たリアリティを一挙にひっくり返すことになりはしませんか」がこの強固さ(硬直さ?)を物語っている...のだが、ここでお気づきになる方はいらっしゃらないだろうか?そのスクリーン上の世界を崩壊させ、観客にまで語りかけて来たヌーヴェルヴァーグ作品のことを。 『幕末』から8年後の1965年に公開されたジャン=リュック・ゴダールの歴史的傑作『気狂いピエロ』の中でこんなシーンがあった。南仏の海岸線をオープンカーで逃走するジャン=ポール・ベルモンドとアンナ・カリーナ。語り合う二人をリアシートから撮っているが、突如ベルモンドが振り向いて一言、二言発する。「誰に言ったの?」と聞くアンナに、「観客にさ」とベルモンド。ここで、スクリーン世界が、崩壊する。 こうした軽い実験をこの大作でやりたかったのだ。寺山修司の映画『書を捨てよ町へ出よう』(昭和46年/人力飛行機舎・ATG)のオープニング−スクリーンの寺山が観客と真正面から対峙し喋り出す−で驚いた人もいるだろう。そうした調和的劇場空間の崩壊を昭和32年に、しかも大手映画会社の記念作品でやろうとしたのが、川島雄三だったのだ(もっとも既に昭和28年の松竹作品『学生社長』で一瞬ではあるが、スクリーンの中から観客を指差す演出が登場しているが)。 この一件についてはフランキー堺のインタヴューにも詳しく語られている。興味深いのはこの案を取り下げた川島があくまで「アタシは自分の考えを通したいのです、だけど(主役の)アナタがそういうから仕方がありません」という態度を貫き通したということだ。主役の意思を尊重して?...とんでもない、私はここに川島特有のレトリックを見る。「自分の案にしなかった為に後から文句が出たり悪評をこうむったりしたら、みんなアナタのせいだ」、つまり自分に責任はない、というわけである。 さて川島がここまでこだわったラストシーンの演出について、幾つかの考察がなされている。一番ポピュラーなものが背景とこの前段で書いた様な日活に対する「撮り逃げ」的姿勢の表出。これは非常に判り易い。そして川島の信条(?)でもあった「積極的逃避」の映像化。これも当てはまるだろう。私も長らくこの2つだと思っていた。 しかしごく最近、3つ目の、壮絶な解釈に出会った。ラストの墓地、墓石は川島が葬り去ろうとしていた故郷「恐山」である、というものだ。それは川島の一生を描いた伝記漫画『栄光なき天才たち』(森田信吾作/集英社文庫刊)にあった。 凄まじくもあるが、なるほどとも思う。実は私はあの場面にひとつの疑問を抱いていたからである。それはそれまで全ての厄介事を巧みに切り抜けて来た佐平次が、ズーズー弁の田舎親父・杢兵衛大尽には何故サッパリなのだろうということだ。 逃げ出すことも出来ず、結局墓場まで一緒に行く羽目になり、そしてそこでも騙し切れない。エピソード自体は古典落語「見立て」からの引用だが、なぜここまで佐平次が冴えないのか。 これは本当に私見なのだが、この場面での佐平次の不振ぶりは、川島にとってあまりにも重過ぎる−己の才覚や洒落心ではかわし切れない−その過去と出生のメタファーだったのではないだろうか。しかしそう考えると、何か、特別な感慨がこみ上げても来る...。 前出のインタヴュー−そんなに昔ではない、平成元年のものである−でフランキー堺は「そうする必要はなかったんです。もうあすこまでで十分に佐平次の心情や作品の訴えは完結していると思うんです。−ありゃ、冗談だったんだな(笑)」と語っているが...フラさんハ判ッテイマセン。本当に、本気で、悲痛な叫びを発しようとしていたのかもしれないのだ...。 |
| 最後に俳優陣について。主演のフランキー堺がジャズドラマー出身であることは前述したし、既に知っていた人も多いだろう。正確に言うと"与田輝雄(ts)とシックス・レモンズ"の出身。ちなみにレモンズには昭和26年頃になんとあの秋吉敏子(p)が在籍していたこともある。フランキーと秋吉は同じバンドの出身者なのだ。自らのリーダーバンドは"シティ・スリッカーズ"、台所用品を"演奏"してしまうスパイク・ジョーンズ(ds)スタイルのコミカルなバンドであった。 しかしこの映画、実はもう一人ジャズメンが出ている。配役と演技からはおよそ想像が付かないだろうが...たった今書いたばかりの田舎親父・杢兵衛大尽こと市村俊幸である。 この人は本職はナット・キング・コール・スタイルのピアニスト兼ヴォーカリストで映画進出は昭和26年の『花嫁蚤と戯むる』(ラジオ映画社)であったと記憶する。印象的だったのはやはりミュージシャン役での出演で、有名な黒澤の『生きる』(昭和27年/東宝)や『嵐を呼ぶ男』(昭和32年/日活)などがある。フランキーとの共演も多く、実は『幕末』の同年に『フランキー・ブーチャンのあゝ軍艦』という川島組のシナリオ・ライター柳沢類寿脚本による軍隊喜劇も残している(監督は春原政久)。 ということは...『幕末』ラストの「俺はまだまだ生きるんでぇ!」と「地獄サ落ちっど〜!」の掛け合いはジャズメン同士の"インタープレイ"−楽器による対話−だったのか?そう考えると妙に嬉しくもなって来る。 「相模屋」を仕切る女将お辰を演じる山岡久乃の冷徹なな母親像はこの4年後、川島の死の前年に撮られた傑作『しとやかな獣』(昭和36年/大映)に繋がる。この人、お茶の間にもおなじみの有名女優だが目が、軽く、狂気を帯びてもいるのだ。『しとやかな獣』での特徴的なアップ・シーンで気が付いた。 川島作品ではこの『幕末』『しとやかな獣』の他、『赤坂の姉妹・夜の肌』(昭和35年/東京映画)などにも出演しているが、起用の理由はもしかしたらあの目元ではないだろうか。つい先日の逝去が惜しまれる。 借金のカタに取られている(!)という印象的な娘おひさ−芦川いづみについてはこちらの第一部「川島その生」で記した。 そして、クックック...貸本屋金造こと小沢昭一大先生。彼なしにはこの映画はなかった!川島が「世界で一番好きな俳優」とまで言った小沢先生の怪演がここでも冴え渡っている。何よりも貸本屋金造がスクリーンに登場すると花が咲いたの如く明るくなる。物語は活気を帯び、あの強烈な声がガンガンと頭に響くのだ。 暗記したわけでもないのに、「品川心中」から生き返った金造の名セリフ「今、生きたての、ホヤ〜ホヤ〜だよォ〜」の前後数分を完璧に覚えてしまった。ヴィデオを見る時いつも合わせて喋ってしまう(笑)。なぜか小沢先生のセリフというのは頭にこびりつくのだ。『しとやかな獣』のピノちゃんも、『洲崎パラダイス・赤信号』の出前持ちの三吉も、かなりのセリフを覚えてしまった。 |
| さて解釈上の要所は未だ未だございますが、このへんで舞台となった「品川宿」を訪れてみましょう。比較写真多数。映画と同じ荒神様のお祭りの日に出掛けて参りました。遊廓についての豆知識もタップリ、『幕末太陽傳』を200%楽しむための2ページです。 駄作の多い川島がなぜここまでハズシの少ない、完成度の高い作品を撮ることが出来たのか?という考察も用意しておりましたが、あまりに長くなるのでそれは駄作側(?)『縞の背広の親分衆』(昭和36年/東京映画)あたりの解説で発表致しましょう。 あとは物語の元になった落語について。「居残り佐平次」を筆頭に、「品川心中」「明け鴉」「芝浜の革財布」「見立て」などが折り込まれておりますが、どこがどの噺かは観て、聴いてのお楽しみということで...。 |
| この『幕末太陽傳』はにっかつから廉価版ビデオが発売されています |
 |
なんと「相模屋」の模型が登場します ロケ地探訪、ここをクリック |