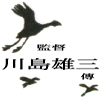 |
99/06/11 監督 川島雄三傳 その生涯 |
| 川島その生 下北の記 |
|
|
| 「川島調」の種子と発芽 |
| 川島雄三の生い立ちを語るとき、そのネガティヴな背景がクローズ・アップされることが多い。近親結婚による遺伝障害、相次ぐきょうだいの夭折等々...。確かにこうした生い立ちが彼の身体上の障害の原因となり、遠回しにその命をも縮めてしまったのは事実である。しかしこの場所ではそれを追求する様には記さない。理由は2つ。 まず、現存する川島家ご一族に対して配慮を払わねばならない。東北の商家の古い因襲と言ってしまえばそこまでだが、当然川島家のご親戚は存命であり、地元でしかるべき要職に就いていらっしゃる方もある。 いち映画ファンに過ぎない電線メーカー勤務の私が、趣味で、現存のご一族の過去をどうこう言うべきではないと考える。私は川島雄三という人物と、その作品を愛する者として、あくまで彼の残したフィルムの中から文章を絞り出して行きたい。 そしてもうひとつ、映画へ、人間観へ繋げよう、ということだ。優れた映画監督で脚本家でもある新藤兼人氏は、『悲しみは女だけに』(昭和33年/大映東京)などの作品で己の一族の物語を映画にし、世に問うている。その他にも自らの生い立ちを映画化した監督、脚本家は洋の東西を問わず数知れない。 川島雄三はその生い立ちを映画にすることはなかったが、我々が何とも云えぬ不思議な魅力を感じている川島映画の物語や登場人物にの「種子」を、彼の一族の中に見出すことは出来ないだろうか。川島の生い立ちの中から、彼の人間観のかけらを見付け、それが育ち、スクリーンの上で発芽するまでを繋げることが出来れば幸いである。 とはいうものの、川島を巡る不幸についてやはり多少は書かなければならないだろう。簡潔に記す。 川島一族は江戸時代中期、近江から下北へ海路を経て移住し、代々商家−食品店兼酒屋−を営んで来たと云われている。そしてその定住の地に選んだのが、のちに川島雄三の生まれ故郷となる青森県下北郡田名部町、現在のむつ市であった。 しかしこの旧家の伝統がひとつの悲劇を生み出してもいた。血統の純粋を守り、財産の分散を防ぐために近親者による結婚を続けていたらしいのだ。その結果−クモ膜下出血に倒れる者、腰椎炎、先天性脱臼といった関節系の疾患、脳の障害から脳膜炎に至る者、若くして肺結核で亡くなる者などが続いたそうだ。 この事象を見て、川島一族について云々するのは間違いである。当時の、江戸末期から明治、大正へと至る日本に於いては「旧家」と云われるものは多かれ少なかれ、こうした因襲にとらわれていたとは言えないだろうか。 川島一族の過去について最もストレートに記したのは川島の助監督から一人立ちした今村昌平氏の文章であると思うが、彼はそこで「旧家がどの家でも過去そうであったように、川島家も、母方の宮浦家も槇家も近親結婚を重ねることで血統の純粋を誇り、資産を散らさず固守したのであろう」と記している。後半よりも前半「旧家がどの家でも過去そうであったように」が重要である。 川島の病についてよく「小児マヒ」と云われるがどうやらそれは正確ではないようだ。「体が弱かった」とはいうが、幼少期には大きな障害はなく、顕著な発病は監督昇進後の昭和21、22年頃の様だ。大学時代から松竹大船、日活を通じての友人、映画監督の西河克己氏は戦前は体には出ていなかったと語り「それでは(体に障害が出ていたら)大船の試験に受かるはずがない」と断言する。西河氏が戦後に復員すると、川島はビッコを引く様になっていたそうだ。 同様のエピソードは吉村公三郎監督の談話にもあり、島津保次郎の助監督に付いていた若き川島が「怒鳴られては走り、怒鳴られては走りで、あのころの彼はよう走り廻っとったでぇ。痩せた川島君の痛々しい姿が目に浮かぶわァ」とも語っている。何よりも有名なのは昭和35年に父の葬儀のため久々に帰省した川島を見て、当の家族たちが「雄三がビッコになっている!」と驚いた、という話だ。 進行性筋萎縮症(進行性筋異栄養症)あるいはシャルコー病(筋萎縮性側索硬化症)が正確な病名の様だ。脳の皮膜から、脊髄、抹消神経を経て筋肉までの線の全体もしくは一部に変化が起こる。「変化」とはなんとも学術的、事務的な書き方だがつまり萎縮であり麻痺である。主に「先天的な原因」に依るものとされ、一旦発病すると治療の効果はあまり期待出来ない。つまり治らない。 ではこれが直接的に「死に至る病」だったのかというと、どうも異論もあるらしい。現に川島の直接の死因は「肺性心」−心臓の衰弱であり、判りやすく言えば「ポックリ病」の様なものだ。更に検死した医師の談話にも興味深いものがある。進行性筋萎縮症は遺伝障害の一種であり、確かに前述の生い立ちと関係があるのだろうが、ではその死も件の家系により運命付けられたものだったのか?これは後程、「その死」で詳説する。川島の生きざまを考える重要な問題であり、正確に語られねばならないことであると思う。 まずは川島を蘇らせる。その出生から記す。そしてあくまで作品と繋げて行く。 |
| ■ 意外な父の影 〜 出生と父 父・徳蔵は注目すべき人物である。結論から言って、私は川島は(意外にも)強力な父権のもとにおり、彼が描こうとしていた男性の姿は、その父・徳蔵なのではないかと考えている。そしてこれはもっと語られていいことだと思う。まず前半は雄三の出生と、その父について記す。 ここで一旦、川島家の家系を遡ってみよう。川島一族をめぐる記述の中で、最も古い人物は文政期の下北・大畑に生きた槇玄範という人物である。 槇家は代々医業を営む家系であったが、この玄範、医業を捨て画家となり各地を放浪したという。妻に作らせた薬を持ち、売薬をしながらの旅であったというから、なにやら後年の「超薬マニア」川島を彷彿とさせる。 |
余談になってしまうが、さらに玄範はお洒落であった点、自分のもの、他人のものという分けへだてがなく、自分の着物を人に与える一方、借金を返さず仕舞いであった等々、エキセントリックな部分で川島との共通点が多い。玄範についての今村昌平の言葉「大変ユーモラスな奇人で、人気のある人であった」はそのまま雄三にも当てはまる。 慶応3年、その玄範の長女・しなが田名部町の商家、六代目・川島忠兵衛の後妻に入る。忠兵衛としなの間には9人の子供が生まれた。その三男・徳蔵は初代大畑村長、宮浦力四郎の四女・ヨシと結婚、三男三女をもうける。その三男が、大正7年2月4日生まれの雄三、というわけだ。 よって玄範は文政の人ではあるが、雄三からは僅か三代しか離れていない。玄範は雄三の曾祖父にあたる。 明治44年4月、当時29歳だった徳蔵は分家をして、田名部に本家と同じ食品店兼酒屋を開いている。ここが雄三の生家となるわけだが、商売の話はさておき、この徳蔵のユニークさたるやお見事である。 最果ての地、田名部で最初に紅茶、コーヒーを飲み、洋食を食い、自動車も買って乗り廻した。写真機も手に入れて現像、焼付までやった。天体の本や、海外旅行の本が好きだった、等々。ほとんどそのまま、川島映画の登場人物ではないか。 |
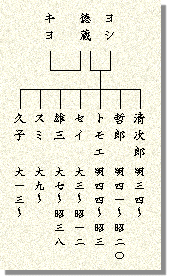 川島一族家系図 |
怪作『貸間あり』(昭和34年)でフランキー堺が演じたスーパーマン"与田五郎"を思い出す。ロールキャベツとコンニャクの製造販売で日銭を稼ぎ、受験術から出産法までのよろずハウツー本を書き、部屋の望遠鏡から天体を眺める。『幕末太陽傳』(昭和32年)に登場した世渡り上手の才人、佐平次を現代に持って来たと云われる与田五郎だが、何故川島がここまで「全能の者」に憧れるのか、当初は判らなかった。しかしこの父・徳蔵の逸話を読むとその与田や佐平次の姿というのは自らの父であり、それを一種の「理想」として考えていたのだと思えて来た。 また写真撮影と現像については川島の趣味として有名だが、『しとやかな獣』(昭和37年)をはじめ、『愛のお荷物』『女であること』『グラマ島の誘惑』『雁の寺』など数々の作品にモチーフとして登場する。しかしこれも父・徳蔵の影響であった様だ。 徳蔵は単なる「地方の道楽者」ではない。病弱だった妻・ヨシにかわり、主婦がわりもしたそうだ。子供たちの下着の繕い、娘たちの着物、履物の面倒も見ていた。『貸間あり』の中で五郎が繕い物などもこなしていたことが思い出される。 |
 |
『貸間あり』 (昭和34年/宝塚映画) フランキー/淡島千景/小沢昭一 五郎の部屋には 天体望遠鏡、地球儀、テープレコーダー ミシン、オルガン、ギター、無線機... |
| 斬新な様に見える川島の「男性像」も意外にこうした好奇心旺盛な「明治の父」を追っていたものではないだろうかと考えるのだが、どうだろう。 徳蔵の言葉に印象深いものがある。「ナポレオンは三時間だそうだが、俺は四時間眠らないと駄目だ。何とかもう一時間つめられないか」である。 川島は助監督達にあの本を読め、この本を調べろと小うるさく言い続けていた。しかし彼らは同時に、毎晩の様に酒の相手をさせられ、中々読む時間などとれない。するとそれを察した川島は、助監督達がそれらの本を読んだのかどうかテストをしたのだそうだ。当然、川島はしっかりと読んでいる。助監督達は皆「あれだけの本を一体いつの間に読んでいるのか」と首を傾げていた。川島のこうした猛烈さも、やはり父・徳蔵ゆずりと思える。 |
| ■ 可憐な乙女の姿 〜 少年期と母、姉 川島雄三の幼少から青年期にかけて、強靱な父とは対照的に実母と姉−女たちとは辛い別れが続いた。これが川島の「原体験」のひとつとなり、その女性観に影響を与えたのか?これについては未だ結論を得てはいない。続いて少年期の川島を辿ってみよう。 7人兄妹の5番目、三人息子の末っ子である雄三は母ヨシに対し手を繋いでねむる程の非常な甘ったれだったという。しかし病弱だったヨシは雄三が五歳半の時に、37歳で亡くなっている。大正12年のことである。のちに雄三が同棲した中村八重司さんがこの実母ヨシにそっくりであったというのは有名な話。雄三の少年期は、まずこの別れから始まったようで、辛い。 |
翌大正13年4月、雄三は田名部小学校に入学。小学校時代の雄三は秀才として名高かった。私は成績表を見たが、これが本当に優秀。10と9が並び、「からっきしダメだった」と云われる「躰操」も8が付いていた。ところがその無口で本好きな秀才、雄三少年を続いて襲ったのは、長姉・トモエの死であった。昭和3年の夏、トモエ17歳、雄三10歳であった。死因は脳膜炎。ふたつめの別れといえる。 それから1年半後、昭和5年4月に雄三は田名部から汽車で1時間南下した野辺地にある旧制の野辺地中学に入学する。成績優秀な雄三は、次兄・哲郎(のちに朝日新聞記者となるも戦死)と同じ県下一の青森中学へも進めたのだが、あえてこの学校を選んだ様だ。野辺地中学の新しさや、人格主義教育をモットーとしていた点などがその理由と云われているが、同時に決して丈夫とは言えなかった雄三の身体を思い「何事かあっても野辺地なら1時間で駆けつけられる」ということも関係していたらしい。 |
 雄三7歳 姉妹、親戚と |
ここで雄三は下宿生活を経験する。更に映画の道を考え、将来への何らかの決意をしたのはこの地、この時であったと思われる。 映画館の下足番と親しくなり、タダで入れる様になったので週に1回か2回というそれなりのペースで邦画−時代劇が多かったという−を観始めている。「映画監督ではなんといっても小津安だ」と言ったり、その小津の作品に出演していたボーイッシュな美形女優、桑野通子(女優・桑野みゆきの母親)にファンレターを出したりしている。また映画雑誌に批評や感想文を投稿していたという話もある。 「映画少年」としての青春を順調に謳歌していたかに思える雄三だがこの頃に、雄三が最も慕っていたいた四つ年上の姉・セイが病に倒れた。 田名部一の美人と云われ(写真を見たが本当に美人だ!)、青森高女を優秀な成績で卒業した彼女だが、卒業後は肺結核のために実家の土蔵の二階に寝込んでいたという。この頃、雄三はたまに実家に帰るとそのまま土蔵の二階に上がり、姉・セイに添い寝しながら長い時間声を出して本を読んであげたそうだ。病の感染を恐れて誰も近づきたがらなかったセイに、である。昭和12年4月、雄三が明治大学専門部文芸科に入って間もなく、セイもこの世を去る。三つめの別れである。 さて、この三度に亘(わた)る女たちとの死別が、映画監督・川島雄三に影響を与えたのか否か。実は私は昔はそんなことは考えもしなかった。急に考え始めたのは川島脚本による喜劇『人も歩けば』(昭和35年/東京映画)を観てからのことだ。 この作品で小林千登勢が健気を絵に描いたような義妹(正確には妻側の親戚)を演じていた。同じ雰囲気を持つキャラクターとしては日活時代の『風船』『幕末太陽傳』『洲崎パラダイス・赤信号』の芦川いづみがいる。芦川出演の3本はかなり前から知っており、私は(愚鈍にも)「芦川いづみという女優の健気なキャラクターが好きなのだろう」位にしか考えていなかった。 |
 小林千登勢 『人も歩けば』 |
 芦川いづみ 『洲崎パラダイス・赤信号』 |
| しかし芦川ではなく、小林千登勢が演じる同様のキャラクターを観て、「川島というのは何故こうした健気で可憐な女性像を描きたがるのだろう?」と考え始めたのだ。ニヒリスト、露悪趣味の川島とはあまりにもかけ離れた「女性像」なのだ。 そして冒頭の一文に戻るが、その関係については未だ結論に達してはいない。しかし、あの『人も歩けば』のラストシーン、テレビの中から「兄さぁ〜ん!」と手を振る少女の姿はあまりにも印象的であった。是非皆さんのご意見を伺いたいところである。 |
 |
監督・川島雄三傳 目次に戻る | |||
| text 2 「明大映研・川島雄三」 準備中 |  | |||