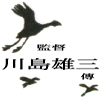 |
99/06/11 監督 川島雄三傳 序説 |
| 川島雄三 前口上 |
|
|
| その名前を初めて聴く人のための |
| 川島雄三−大正7年(1918)2月4日、青森県下北郡田名部町に生まれる。明治大学映画研究部を経て昭和13年、松竹に入社。島津保次郎、吉村公三郎、小津安二郎、野村弘将、木下恵介らの助監督を勤めたのち監督昇進試験に首席合格。昭和19年『還って来た男』(織田作之助原作)で監督デビューを果たす。 文芸・喜劇映画を中心に24作品を残すが、昭和29年日活移籍。在籍は短かったがこの時期の作品には佳作が多く、いわゆる「川島調」の発芽は日活時代であったといわれる。そして、日本喜劇映画の金字塔と賞せられる『幕末太陽傳』(昭和32年)を最後に再度東京映画(東宝系)に移り、自由な社風の中で数々の佳作、珍作を残す。この時期に撮られた大映への出向作品『雁の寺』『しとやかな獣』(共に昭和37年)も評価が高い。 監督昇進のころから進行した奇病「進行性筋萎縮症(進行性筋異栄養症)」の影響もあり絶頂期といえる昭和38年6月11日未明に東京・芝の自宅で急死。前夜は映画関係者と銀座で呑んでいた。享年45歳。遺作は死の5日後に封切られた『イチかバチか』(東宝)。監督生活は19年で作品数51本、急死によって実現しなかった監督予定作品が3本ある。 斬新、洗練、前衛を極めた作風は死後三十数年を経た現在でも信奉者が多い。助監督として影響を受けた者に今村昌平、浦山桐郎、中平康ら、脚本で師事した者に藤本義一、親交の篤い俳優にフランキー堺、小沢昭一、三橋達也らがいる。 小児マヒ患者の為の共同募金「あゆみの箱」は川島の死を悼んだ映画関係者が始めたものだが、しかし、もしかしたら、川島は嫌がるかもしれない。洒脱と皮肉を愛し、叙情的な慈悲を嫌った。それが川島雄三である。 |

川島雄三 (1918-1963)
| 川島に狂ってしまった人、と云う者が居る。調べてみると少なからず居る。私もそのひとりである。決して有名とは云えないこの夭折の映画監督に、人は何故ゆえに狂わされるのだろうか? 昭和38年6月11日没、享年45歳。19年という決して長くはない監督人生に於いて、彼が残した作品は51本である。私は現在その中の44本を観ているが...大傑作4本、佳作3本、傑作の様な駄作のような不思議な作品が11本、そして大駄作が13本、掴みどころのない作品が11本と分類している。 注目すべきは大駄作の多さだ。その多くは会社から任されたプログラム・ピクチャー、軽喜劇の類で、前者は核となるスターを活かしきらず凡庸で、後者は雑な造りの上にシナリオが稚拙で「どこで笑えばいいのか判らない」という感じだ。 ムラっ気の多い人なのだ。撮影記録を見ると「この作品では全くやる気がなかった」というものが少なくない。そして出来上がった作品を観ると...確かに全く面白くない(苦笑)。通常ここまで駄作に当たれば、その監督を追うことなど止めてしまうだろう。しかし、そんな駄作に当たろうとも、「全作品を観てみたい」と思わせるのは、川島の大傑作から感じられる才気、いや非凡なる異能さにある。あれを「鬼才」と呼ばずして、何と呼ぼう。 川島の大傑作、それは本当に凄い。鑑賞中は心臓が高鳴り、瞬きさえも忘れ、エンドマーク後にも身体が震える程だ。「叩きのめされる」−そんな表現がぴったりかもしれない。そして未見の作品にも、「何か」があるかもしれないと、期待してしまうのだ。 人は巨匠・黒澤明の映画を「パワフル」だと云う。確かにそう思う。しかし川島の映画も同様に、いや時には黒澤以上にパワフルなのだ。しかしその質が全く違う。黒澤のパワフルさが映像と物語のダイナミズムが生み出したものだとすると、川島のそれは正に対照的、人間の心理を深く追求し、観る者の思考に直接作用する、そんなパワフルさなのだ。 川島映画には派手な合戦も、逞しい刑事も出ては来ない。閉ざされた−少々奇妙な−空間で、どちらかといえば少なめの−少々奇妙な−登場人物を巧みに動かし、喋らせて、観る者の心をグサリと突き刺す。それが川島映画だ。そしてそれは世界中のどこにもない、唯一無二の芸術である。 更に川島精神の根幹を成すニヒリズム、逃避願望に惹かれる者も多いだろう。全くもって優等生ではないのだ。徹底的に偏屈で執着気質。奇妙なもの、奇妙なことをこよなく愛する。洒脱、前衛、斬新を信条とする。しかもそれこそが映画の、延いては人間の「真実」であるという不思議な哲学(?)もある。一種封建的な日本の映画界で、よくぞこんな人物が「企業内監督」として生きて行けたと不思議に思う程だ。 優等生的思考に反旗を翻した偏屈さ。私が惹かれているのもこの部分である。「何十年も前にこんな人間が居たんだから、私ももっと無茶苦茶をやっても良いのだ」と心強く(?)なって来る。もっともそんな川島映画、「現代の戯作」で収まっているうちは良いが、時にあまりに行き過ぎて「醜悪趣味」と思われてしまうこともあったが。 誤解のない様に言っておくと、傑作は良し、駄作は駄目、そんな単純な二元論で片付けられる監督ではない。その中間に位置する様な、「不思議な作品」たちにもなんとも言えぬ魅力がある。 これは少々判りにくい「魅力」なのだが、古いファンの中にはそれを追求している者も多いだろう。それらの作品の中にも−更には前述の大駄作の中にさえも−何回か観ているうちに「川島調」とでも云うべき不思議な味わいが感じられたり、大傑作に結びつくひとつの伏線を発見したりするのだ。まぁ、残念ながら何本かの作品は何回見直しても最後まで駄作のままなのだが。 川島の奇病とそれによる悲劇は、ここにはあまり書くつもりはない。川島は極めて不自由な身体でありながら、周囲の人間が憐憫の情をもって接することを徹底的に嫌った。「あのような身体でこんな映画を撮った」という言い方も出来るが、その視点はフェアではない。 むしろ我々は川島の映画をあくまで客観的に分析し、論じるべきだろう。我々が行うべきは、川島が不覚にも失ってしまった数十年という時間を、観ること、論じることによって補うことである。 あえてその生涯と作品を絡めるならば...ひとつの命題を提示しよう。川島の少々極端な生への執着から、我々は何かを知る、何かを感じるべきではないかという大きな命題を。 難しい。全くもって難しい。川島映画から受けるなんともいえない様な魅力を言葉にすることなど...。そもそも「なんともいえない」ものをどういえば良いのだ(笑)。 ともかく、観る事から始めよう。川島はあまりにも、観られ、語られなさ過ぎる。 |
 |
監督・川島雄三傳 目次に戻る | |||
| text 1 「川島その生〜下北の記」に進む |  | |||