| Back to the menu |
 |
98/07/05 若人のための 日本映画入門 戦後黄金期編 |
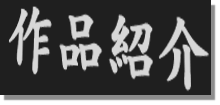
巨匠・黒澤明の世界
| 出 演 |
音 楽 |
撮 影 |
脚 本 |
原 作 |
監 督 |
天 国 と 地 獄 | ||||
| 藤 原 釜 足 東 野 英 治 郎 菅 井 き ん 他 |
仲 代 達 也 石 山 健 二 郎 山 崎 努 |
三 船 敏 郎 香 川 京 子 江 木 俊 夫 |
佐 藤 勝 |
中 井 朝 一 斉 藤 孝 雄 |
黒 澤 明 橋 本 忍 小 国 英 雄 久 垣 栄 二 郎 |
エ ド ・ マ ク ベ イ ン |
黒 澤 明 |
|||
| 昭 和 三 十 八 年 東 宝 |
| 黒澤現代物の最高峰 |
| 世紀の名翻案 |
| 小、中学校の頃、親に連れられて日本映画を随分観た。両親とも映画好きで頻繁に出掛けていたので、仕方なく一緒に観ていたのだ。もう20年も前のことなのか、やれやれ。 『二十四の瞳』(昭和29年・松竹大船)、『野火』(昭和34年・大映)、道徳的で教育的にも「観るべき映画」だといえる。大人のドラマも観た。『家族』(昭和45年・松竹)、『忍ぶ川』(昭和47年・東宝/俳優座)、『約束』(昭和47年・松竹)など、ちょっと難しかったがいくつかのシーンは今でもはっきり覚えている。さすがに『旅の重さ』(昭和47年・松竹)とまでなると、ちょっと難解ではあったが...。 そんなどの作品とも違う、強烈な印象を与えたのがこの『天国と地獄』(昭和38年・東宝)であった。中学1年の時に、母親に連れられて今はなき地元・テアトル鎌倉で観た(母親はなぜか終始無言で、どんな映画を観るのかは判らなったのだが)。ショックだった。ショックが強すぎて熱を出して寝込んでしまった程だ(笑)。 まず舞台に痺れた。私も知っていた横浜や鎌倉の、しかし大昔の風景。それが今よりもなぜか格好良く見えた。特急こだま号(新幹線ではない、東海道線の特急である)を使った犯行にも驚いた。心臓がはち切れそうだった。好奇心旺盛な中学生には、最高の体験であったのだ。 思えば親に付いて行って観る日本映画か、友人と観る『ジョーズ』や『スター・ウォーズ』しか知らなかった私が、自主的に映画というものを探り、観て行こうと考えた...いわば「映画の凄さ」に気付いたのはこの『天国と地獄』がきっかけだった。30歳を過ぎ、こうして駄文を書いているのも、この一本があったからかもしれない。 横浜港を見下ろす高台に、ナショナル・シューズの常務・権藤(三船敏郎)の邸宅はあった。美しい妻(香川京子)と、一粒種の純(江木俊夫)に囲まれて、その生活は幸せそのものだった。野心旺盛な権藤は、次期社長の座を狙っている。実はこの邸宅はその資金のためにすでに抵当に入っているのだった。邸宅だけではない、全ての財産を懸けて、間もなく開かれる株主総会に備えていたのだ。 そこに一本の電話が入る。「あなたの子供は私がさらった。三千万円用意しろ」。うろたえる権藤。しかしそこに、誘拐された筈の純が帰ってくる。ほっとしたのも束の間、権藤の頭を不吉な思いがよぎる。純と一緒に遊んでいたお抱え運転手・青木(佐田豊)の息子、進一がいない!再び電話のベルが鳴る。「子供を間違えた。だが、誰の子だろうとかまわない。三千万円はお前が出すんだ」。 権藤の手には、全財産を懸けた買い占め資金、五千万円の小切手があった。これを使えば進一は助かる。しかし、それは権藤自身の身の破滅を意味する。 おお、段々と観た時の事を思い出して来た。最初は単なる誘拐ものかと思ったのだ。ところが、誘拐されたはずの純がけろりと帰ってきたあたりから、「何だ、何だ」という感じになって来た。そこで思わず身を乗り出した記憶がある。確かその直前に、後ろ姿を観た母親が二人を取り違えるという伏線があったのでは...。 夜になり、デパートの配送員に化けた横浜・戸部署の刑事たちが到着した。三度目の電話が入る。「子供は元気だ。今、声を聞かせる」「おとうちゃん、おとうちゃんいる?!」。それだけ聞かせると、犯人は電話を切った。権藤にしがみつき、どうにか助けてくれと頼む青木。しかし権藤は決断出来ないでいる。 夜が明けた。権藤の迷いは続いていた。ところがそこで腹心、河西(三橋達也)の裏切りを知る。反権藤派の重役たちと通じていたのだ。それをきかっけに権藤は決断、犯人からの次の電話に「金は払う」と応えた。「かわりに子供の元気な姿を見せろ」。 犯人からの最終通告が来た。厚さ7センチの革鞄を2つ用意しろ、三千万円をそれに入れて、明日の特急第二こだま号に乗れ。子供の姿も見せるという。一聴すると不思議な通告だ。「どこまで行くんだ」「乗ればわかるよ。権藤さん」。 警察は鞄に紫色の煙を上げる特殊な薬剤を組み込もうとした。すると権藤は、薬剤と鞄を取り上げて自ら縫い始めた。今や常務の権藤だが、実は見習工からの叩き上げなのだ。古い道具を出し、「昔はこうしていたんだ」と、黙々と縫い付ける権藤。この「今と昔」に対する三船の説得力は凄かった。この作品中、有数の名シーンである。 権藤と刑事たちを乗せた特急こだま号が出発した。犯人からの具体的な指示はなにも与えられていない。そこに犯人からの車内電話が掛かる。「子供は酒匂川の鉄橋のたもとで見せる。渡り切ったところで、鞄を洗面所の窓から投げろ。7センチ開くはずだ」。 計算づくであった。目の前に犯人を見ながら、追いかけるこも出来ない。犯人と、進一の横を特急こだま号は時速100キロで疾走する。権藤は窓の隙間から鞄を投げた。犯人の手がかりとなるもの、それは刑事達が運転席、車掌席に身を潜めて撮影した8ミリと写真だけだった。 さて、この疾走する特急から8ミリを撮るというモチーフ。ごく最近、とあるところで使われていた。森田芳光監督の『(ハル)』(平成8年・光和/東宝)である。なかなか巧い引用で、思わずニヤニヤしてしまった。『(ハル)』のカップルが映画ファン仲間であった、ということなども想起されたし。 権藤と刑事たちは次の熱海駅から酒匂川に戻る。そこには、進一がいた。ここまでで十分映画1本分のストーリーがあるが...なんと物語はここから始まるのだ。警察の捜査が開始された。目撃者、怨恨、電話の分析...。そんなある日、ベランダで遊んでいた純と進一が声を上げる。「紫色の煙が出てるよ」。 それは病院の煙突からだった。刑事が走る。そこでそのゴミを燃やしたのが、若いインターンの竹内(山崎努)であったことが判明する。しかし、ここで警察は策を講じる。今、竹内を挙げても誘拐だけで最高十五年。この直前に、8ミリに映っていた共犯者2名が、ショック性のある高純度の麻薬によって殺されていた。これも竹内の犯行と考えていい。この凶悪犯を極刑にするには、しばらく泳がせて麻薬殺人を再現させるのだ。そして、竹内に最後の夜がやって来た...。 ストーリーもさることながら、その映像にも取り憑かれた。権藤宅に入る刑事たちが、犯人の監視を逃れるために「横浜高島屋」の配送員に扮していたこと(この「横高」(ヨコタカ)という設定には涙が出る。絶対に三越でも松阪屋でもない。横浜といえば西口の高島屋なのだ)、元祖・無国籍バー「根岸屋」の店内、さらにそのフロアで踊りながらヤクを受け渡しするシーン、特急こだま号から観た酒匂川の土手、夜の伊勢佐木町で犯人・竹内が皮肉にも偶然に出会った権藤から煙草の火を借りるところ、等々。強烈にこびりつき、目を閉じればすぐにでもプレイバック出来る。 ところが、改めて考えてみると、私はこの映画をたった二度しか観ていないのだ。中1のとき鎌倉で、中3のときTVで、の二回である。現在に至るまで20年以上にわたり、この映画のことを熱く語って来たが、それはたった二回だけ観たこの中学時代の記憶に基づいていたのだ。それ程までにこの作品は強烈な、まさにこびりつく様な印象を残した。 |
 |
中央・山崎努 |
| この映画の原作となったのはエド・マクベインのサスペンス小説「キングの身代金」である。確か原作は犯人のひとりがハム(アマチュア無線家)で、彼の傍受した警察無線から刑事の行動が漏れるというストーリーだったと思う。この設定は『天国と地獄』では全く使われていない。下敷きにはされているかもしれないが、横浜と特急・こだま号という舞台を得て、黒澤はよりスリリングな大傑作に作り直したのだ。 地元・神奈川の人間ならば、犯人のインターン・竹内が地元の名門・横浜市立大学(旧・横浜医専)の出身ではないか、などという深読みも楽しめる。高島屋といいい、これといい完璧なまでに日本の、横浜のリアリティを持っているのだ。「世紀の名翻案」である。 そうだ、捜査の中心となる田口部長刑事(石山健二郎)のニックネームが「ボースン」、港の水夫長だったことも思い出した。港町・横浜でしか考えられないこのセンス、最高である。 最後に若い人達に一言。劇中に登場する「根岸屋」を観て、「こんな店をやりたい!」と考え、実際に創ってしまったのがバー「インクスティック」の経営者、松山勲氏(1950-2003)である。 '80年代カルチャーを代表した「インク」や「トゥールズ・バー」「レッド・シューズ」などが、今の「クラブ」に発展した。現在楽しんでいるクラブ・カルチャーの出発点が、この『天国と地獄』と「根岸屋」だったのだ。観た方がいい。 |
| 出 演 |
音 楽 |
撮 影 |
脚 本 |
監 督 |
酔 い ど れ 天 使 | ||||
| 笠 置 シ ヅ 子 殿 山 泰 司 他 |
小 暮 実 千 代 中 北 千 枝 子 千 石 規 子 |
志 村 喬 三 船 敏 郎 山 本 禮 三 郎 |
小 沼 渡 |
伊 藤 武 夫 |
黒 澤 明 植 草 圭 之 助 |
黒 澤 明 |
|||
| 昭 和 二 十 三 年 東 宝 |
| 女性に観て欲しい男の物語 |
| 音楽的魅力もたっぷり |
| 「黒澤が観たい」という女性に、私はこの作品『酔いどれ天使』(昭和23年・東宝)を勧めている。最愛の『天国と地獄』は、確かに傑作だがちょっと「男の子向き」という感じがするのだ。この『酔どれ..』は女性も楽しめる、いや、むしろ女性にこそ観て欲しいという感じもする。 メタンガスの噴き出す大きな池がある。むせ返るような夏の夜、訥々としたギターの音色が流れている。池の横には闇市と、一軒の病院。医師の真田(志村喬)は薬用のアルコールを呑んでしまう程の酔どれだが、心は天使のようにやさしい。 ある日、ピストルに撃たれた闇市の顔役・松永(三船敏郎)がやってくる。そこで真田は松永が肺病に侵されていることを知る。養生をするように勧める真田の首を、松永は締め上げる。実は松永は怖いのだ。 そこに入って来たのは美しい看護婦・美代(中北千枝子)だった。美代はかつて、現在服役中の松永の兄貴分・岡田(山本禮三郎)の女で、身体をぼろぼろにされこの病院にかくまわれているのだった。 数日後、泥酔した松永がレントゲンを持って病院に来た。酒の力を借りなければ、自らの身体をさらけ出せない松永。レントゲンを観る真田...松永の病状は思いのほか重かった。 ある夜のこと、腐った池にいつもより巧いギターの音色が響く。ギターを貸した男が、それを弾く人相の鋭い男に訪ねる。「巧いねぇ。なんて曲だい」「『人殺しの唄』さ」岡田である。 岡田の出所によって街の均衡は変わりつつあった。子分達はもちろん、松永の情婦・奈々江(木暮実千代)までが岡田に付こうとする。松永はついに喀血。真田は松永を病院に引き取る。 数日後、いよいよ岡田が病院にやって来た。美代の居場所を嗅ぎつけたのだ。岡田に頼み込んでどうにかその場を収めた松永。しかし、これで、完全に松永は劣勢になる。 弱くなったやくざ者は哀しい。闇市の花屋で一輪の薔薇を失敬するも、店の主人に「お代を...」と言われてしまう。かつては我が物顔だった街も、今ではすっかり岡田の天下であった。 情婦・奈々江の態度を引き金に、松永は最後の戦いを岡田に挑む。まさに命を懸けた、壮絶な死闘であった...。 封切りは昭和23年4月27日、敗戦から僅か2年半ほどのことである。物資すらなかったあの時代に、こんなに面白い、こんなにファッショナブルな映画がこの日本で撮られていたのか。信ずるべきは表現者たちの才能と信念、ということだろう。 |
 |
三船敏郎、志村喬 |
| たった今、「ファッショナブル」と書いたが、この映画、全く古くない。そして、音楽面での見どころも多い。ペースメーカーになっているギターも面白いが、松永と岡田が根城にするダンスホールのシーン、笠置シヅ子本人が登場して、フルバンドをバックに歌う「ジャングル・ブギ」は圧巻であった(ここで東京スカパラダイスオーケストラのカヴァー・ヴァージョンが原曲に忠実であったことに気付く)。 しかしこれも単なるサービスショットとして挿入されているわけではない。既に病状が悪化し自棄になった松永が、この曲で女給を相手に踊り狂い、病院に帰るなり真田に怒鳴られる。ド派手な演奏がブツリと切れて、真田の「馬鹿モノッ!」に繋がる編集は見事であった。 しかし面白い設定である。肺病病みのやくざと、酔どれの医者。人間の持つ純真さと脆さがこのふたりに凝縮されている。時に三船28歳、初の主演作品であった。 なお、さすがにこのろこは志村も(少しだけ)若い。荒くれ者・三船と渡り合う志村の勇気も見ものである。そして忘れてはいけないのが、松永を見守る飲み屋の女・ぎん(千石規子)である。この物語、実は男の弱さと無軌道さを、女の視線から描いたものなのかもしれない...。 |
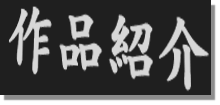
続いて『野良犬』とその他の作品をご紹介
上のテロップをクリックして下さい