| Back to the menu |
 |
98/07/05 若人のための 日本映画入門 戦後黄金期編 |

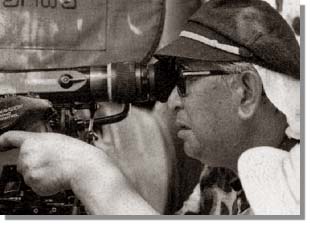
撮影風景
 |
| 「黒澤さんなんて『七人の侍』一本で総理大臣級の待遇をしてもいいと思う」−作家・井上ひさし氏は語る。 日本映画界の大御所、黒澤明と僕らの接点を探ってみる。時代劇映画が多い。時代劇?老人じゃあるいまいし、興味ないなぁ。現代劇もある。そうは言っても昔の話、かったるいんじゃないの?全て誤解である。黒澤のシャシンは熱い。いつまでも、煮えたぎる様に熱い。この熱さは21世紀になっても決してさめることはないだろう。 そう、まさに、熱狂的である。時代劇を観てみる。ストーリーの面白さ、映像の素晴らしさにあっと言う間に引き込まれる。時代劇を敬遠していた自分が愚かに思えて来る。時を超える黒澤の時代劇は、民族までも超越する。『七人の侍』(昭和29年・東宝)を西部劇に置き換えたのが、ユル・ブリンナーの名演で知られる『荒野の七人』(昭和36年・米)である。昭和36年の『用心棒』(東宝)は、遠くイタリアでマカロニ・ウエスタン『荒野の用心棒』(昭和40年)となった。この時主演したクリント・イーストウッドのメイクは、明らかに『用心棒』での三船敏郎を意識したものであった(もっともこの作品は「盗作」として裁判沙汰になったが)。 現代劇を観てみる。舞台は昭和20〜30年代だが、全く古さは感じさせない。古さどころか音楽が、衣装が、ヘアスタイルが、むしろファッショナブルに思える程だ。セリフも芝居も違和感がない。「黒澤組」の名優たちの芝居は洗練を極めているのだ。 これから紹介する数本の作品を、とにかく観て欲しいと思う。そして黒澤に狂って欲しいと思う。テクノ好きの大学生も、ロック好きのOLも、ジャズ好きのサラリーマンも、平成を生きる全ての人々の心を、黒澤の名画は狂わせる。それだけの力があるのだ。 「世界のクロサワ」−この言葉の本当の意味が判るはずである。 |
| 1998年9月7日追記 |
黒澤明監督。昨日逝去。合掌。 |
 |
| ■ 「監督・黒澤」の誕生 黒澤明は明治43年、東京・東大井に生まれた。父・勇は陸軍の体育教官、明は四男四女の末っ子であった。京華中学卒業後、プロレタリア美術研究所に通い二科展にも入選。黒澤の絵コンテの巧さは有名だが、もともと画家としての修行を積んでいた人なのだ。 当時、兄・丙午が映画の弁士をやっており、兄のパスで欧米の芸術映画を観まくったそうだ(この丙午はのちに伊豆で自殺している)。そして、PCL(東宝の前身)を受験。助監督として入社した。時に昭和11年2月、「二・二六事件」直後のことである。 山本嘉次郎監督などに付いた後、昭和17年、『姿三四郎』(出演・藤田進、大河内伝次郎、他)で監督デビューを果たした。当時は戦時下ということから審査がきつく、この『姿三四郎』も「監督法監督登録試験」の対象となった。その時の審査員、松竹の小津安二郎監督は黒澤の手腕を「百点満点で百二十点」と評した。 初期の重要な作品に『銀嶺の果て』(昭和22年・東宝)がある。この作品、黒澤の監督作ではない。同期入社である盟友・谷口千吉の初監督作品なのだが、黒澤が原作・脚本を記し、志村喬、三船敏郎、小杉義男というのちの黒澤組の名優たちが出演していることから黒澤の重要なキャリアのひとつに数えられることが多い。実際のところは親友・谷口に黒澤が餞(はなむけ)としてシナリオを書き下ろした、ということらしい。 この作品が重要なのは「黒澤と三船」という世紀の邂逅があったからである。三人の銀行強盗が白銀のアルプスに逃げ込む、極限状態の下で仲間割れを起こし...というダイナミックな物語の中で、ギラギラとした演技で周囲を圧倒したのが若き三船であった。「黒澤さん、惚れちゃいましてね。『次の作品に貸してよ』って」、谷口監督は語る。 そしてその次回作が、『酔いどれ天使』(昭和23年・東宝)。コンビ誕生、三船初主演の記念すべき作品である。以降、黒澤・三船コンビは実に15本の作品を残した。ここでもうひとつのコンビも生れた「三船と志村」である。肺病病みのチンピラ松永(三船)、医師として彼を救おうとする真田(志村)、黒澤作品の典型となる対比の構図が既にここで築かれていた。この二人については後述する。 ■ 「世界の黒澤」の誕生 二人の優れた演技者を得た黒澤は、『静かなる決闘』(昭和24年・大映)、『野良犬』(昭和24年・新東宝)、『醜聞(スキャンダル)』(昭和25年・松竹)といった「三船と志村」のコンビ作をコンスタントに発表、そして昭和26年9月、『羅生門』の第十二回ヴェネチア国際映画祭金獅子賞(グランプリ)受賞で日本中の、いや世界中の話題をさらった。 この『羅生門』で黒澤は数々の実験を試みている。技術的な部分ではアフリカ探検映画を参考にしたという疾走するカメラ・ワーク、消防車三台で降らせたという墨汁入りの雨、そして話題となったのが「太陽に直接カメラを向ける」という手法である。太陽の撮影は「フィルムが焼ける」と長らくタブー視されていたもので、黒澤が世界で初めて成功。以降、世界中で流行したそうだ。 黒澤の実験は技術面だけではなかった。この物語、「ことの真相」がわからないまま終わってしまうのだ。平安時代のこと、ある侍が殺される。盗賊や侍の妻、杣売りなどが登場するが一体誰の言うことが本当なのか判らない。芥川龍之介の「藪の中」を橋本忍と共に脚本化したこの作品、観客の「突き放し方」がまるでヨーロッパ映画の様である。海外での評価も納得出来る。ヴェネチアに留まらず、翌昭和27年の米アカデミー賞最優秀外国映画賞も受賞している。「世界の黒澤」の誕生である。 ■ 絶頂期、そして... 以降約15年間にわたり、黒澤は絶頂期を迎える。昭和27年に「命短し、恋せよ乙女」で知られる名作『生きる』(東宝)、最高傑作といわれる『七人の侍』(東宝)が、そのわずか2年後の昭和29年、昭和32年にはシェークスピアの「マクベス」を戦国時代に置き換えで翻案した『蜘蛛巣城』、更に同年、今度はゴーリキーの『どん底』を江戸時代の長屋ものに翻案、意欲的な活動で周囲を唸らせた。 昭和36年、37年には人気の高い娯楽活劇『用心棒』(東宝)、『椿三十郎』(東宝)を続けて発表。昭和38年、スリル溢れる現代物の『天国と地獄』(東宝)で映画ファンを魅了し、昭和40年、再び時代劇の大作『赤ひげ』で本領を発揮した、ところまでは、よかった。 昭和42年から44年にかけて黒澤は日米合作、黒澤プロ/二十世紀フォックス製作の『トラ・トラ・トラ!』に翻弄される。真珠湾攻撃を描くこの作品に黒澤は日本側監督として参加していた。しかし、撮影は困難を極めた。数々の問題があったのだ。 まずはキャスティング。プロの俳優ではなく会社社長などの一般人を起用した大胆なキャスティングは周囲の俳優たち、盟友・三船にまで波紋を投げかけた。さらには制作費の安さから使用した東映京都撮影所の問題。完璧主義者で「天皇」とまで言われた黒澤の映画作りと、任侠映画でじゃんじゃん稼ぐ東映の作法は全く相容れないものだった。そんな行き違いは合作先の米国側二十世紀フォックスとの間にも生じ、契約上のトラブルも発生して遂に黒澤は降板を余儀なくされる(代わりの監督は升田利雄、深作欣二)。 この時に「降板の理由は黒澤のノイローゼ」というニュースが流れた。この件については契約書中に「不測の事態の場合は保険会社から損害に対して賠償金が降りる」とあるのを見た黒澤プロ側が、これ幸いと黒澤をノイローゼに「仕立てた」という説もある。しかし、その2年後、衝撃的な事件により、黒澤の「病状」が心配された。昭和46年12月22日、自宅風呂場で首筋などを切り自殺未遂を図ったのだ。 ■ '70年代から現在 自殺未遂の原因は何だったのだろうか。「日本映画の衰退」がその一因であるとも言われている。1970年代に入り、映画人口は激減、最盛期の実に5分の1まで減少する有り様だった。自殺の前日には『羅生門』を撮った名門・大映が倒産している。そして件の「トラ・トラ・トラ!」の騒動も黒澤を疲弊させるものだった。 一命を取り留めた黒澤は、ゆっくりと、映画づくりを再会した。昭和50年に5年ぶりの新作『デルス・ウザーラ』(ソビエト)、昭和55年にカンヌ映画祭グランプリ受賞作品となった『影武者』(東宝)、以降約5年おきに新作を発表。最新作は平成5年の『まあだだよ』(大映/電通)になる、が、私の黒澤は自殺未遂の前年に発表した初のカラー作品でもある『どですかでん』(四騎の会)で終わっている。 不思議なのだ。昭和23年の『酔いどれ天使』から、昭和40年の『赤ひげ』までは全く同じ「熱さ」で、全く同じ「黒澤調」で撮られている。この期間の17本はいずれおとらぬ名画である。しかし、異色作『どですかでん』の前後で何かが変わった。あくまで私見に過ぎないが、これに続く1970年代始めのブランク以降、かつての「熱さ」が感じられなくなってしまったのだ。 その原因が何であるか、そこで変わったのは何であるか、それを考えることは、日本映画全体の変化を考えることと同じに思える。残念ながら私はまだ、簡単に説明出来ることばを見付けてはいない。あくまで私見に過ぎないが...。 |
 |
| 黒澤作品に欠かせない二人の名優、三船敏郎と志村喬について考えてみる。この二人の関係は「静と動」...いや、ちょっと違うな。「熱と冷」、うーん、近いがちょっと...そう、「激と穏」と言ったところか。 ある時は目に見えるかたちで、またある時は内なる激しさで、強烈な印象を与える三船に対し、志村はいつも「穏」であった。しかし、ただ穏やかなだけではい。ある時は三船と同等に、またある時は三船以上に、我々にその印象を残すのだった。 「熱と冷」という表現も捨てがたい。例えば名作『七人の侍』(昭和27年・東宝)、若さのあまり無軌道な行動に出る三船の「菊千代」を、鉄壁の冷静さで抑えるのが志村の名将「勘兵衛」だった。この関係は、コンビの傑作である『酔いどれ天使』(昭和23年・東宝)、『野良犬』(昭和24年・新東宝)でも同じである。 熱き三船と、それを知的に冷静に冷ます(醒ます)志村。そのバランス、その起伏によって黒澤作品は成り立っているとも言える。どうも志村が気になる。志村から行こう(笑)。 志村喬−不思議な俳優である。全くもって不思議。「脇役のようで、脇役でない」のだ。志村には脇役俳優とは明らかに異なる主役の「華」がある。色男ではないし、若手でもない。しかし志村の存在感は明らかに「主役」のそれだ。 強弱の使い分けも凄い。「命短し、恋せよ乙女」で知られる名作『生きる』(昭和27年・東宝)の悩める市役所職員を観た人は「なんと弱々しい人なんだ」と思うだろう。そして前述した『七人の侍』の強靱な名将・勘兵衛を観ると...これが同じ人だと思えるだろうか!。 明治38年(1905)生まれ。舞台俳優から映画に転じ、初期は新興キネマの無声映画に出演していた。映画デビューは昭和9年、出演作は私が調べただけで400本以上ある。黒澤作品での名演が有名だが、実にその数十倍に及ぶキャリアを持つのだ。穏やかな才人に見えて、実は戦時中、特高警察に拘束された経験もあるという。昭和57年に他界。 笠智衆、殿山泰司、大滝秀治等々、実力派男優数々いれど、この志村喬の魅力は容易には言葉で表せないように思う。「説明不能の魅力」があるのだ。バイプレーヤー(脇役俳優)と呼んでしまっていいやら、悪いやら...。 |
 『生きる』の志村喬 |
上等兵・三船敏郎 |
| そして三船敏郎−この人の魅力は明解、「生まれながらの主役」だ。上の写真を観ていただきたい。どう見ても戦争映画のスチールだが、これは東宝入社前、陸軍航空隊時代、まだ一般人だったころの三船である。これを持ち歩き、希望する兵隊仲間にサイン入りで配っていたというのだから、その度胸たるや立派なものである。 大正9年(1920)中国・青島で生まれ、満州・大連で育った。家業は写真館で、自らも撮影をこなす。昭和15年から陸軍航空隊において兵役に就くが、配属は写真部であったそうだ。「外地育ち」は三船を解くキーワードのひとつで、その生い立ちがダイナミックな三船のキャラクターを育てたとも言われている。共演した女優達は「野性味もあって表情も豊かで、まるで外人の様だった」と語る。三船の魅力のひとつ、それは「エキゾティシズム」である。 そんな生まれながらの名優(?)が、デビューのきっかけは「カメラマン助手希望として東宝撮影部に出した履歴書が、誤って第一期ニューフェースの面接に回ってしまった」からだと言うから驚く。復員から間もない昭和21年のことである。デビュー作は『銀嶺の果て』(昭和22年・東宝)、それからの活躍は前述の通りである。 入社後も暫くは撮影部移籍の可能性があったそうだ。しかし、御存知の通り、移籍などはしなかった。「撮影部・三船」ではなく、「世界の三船」となったのだ。 三船は我々の世代からはなかなか正当な評価を受けにくい人かもしれない。昨年12月の逝去から、リアルタイムで知っている三船を遡って思い出すと...ボケていたと言われる晩年、後妻に去られた男、高級布団のCMで金髪モデルに向かって「う〜ん、寝てみたい」、そして『1941』('79年・米)でのトンマな軍人役...こんな認識から「世界の名優」を実感することは確かに難しい。 しかし、だからこそ、旧作を観よ!初の主演作『酔いどれ天使』を観た女性ファンは、そのクールさに惚れ惚れとするだろうし、『七人の侍』では演技者・三船に腰を抜かすだろう。『用心棒』(昭和36年・東宝)では腹を抱えて笑い(ユーモアも三船の大きな魅力だ)...キリがない。言いたいことは只ひとつ、「三船の天才に気付くべし」だ。黒澤を観ずして三船を語るべからず。 志村、三船とも残念ながら故人だが、スクリーンの上では永遠の命を与えられている。今からでも十分、遅くはない。 |
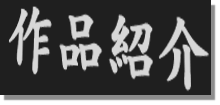
それでは次頁より代表的な作品をご紹介致します
上のテロップをクリックして下さい