

| インターネットロックページ共同執筆 新譜/名盤クロスレヴュー |
| 月刊 ロック・クルセイダーズ No.027 Feb.'02 |
| 2001/02/20 Updated |
|
| ||
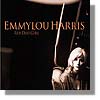 |
今月は新譜の月です Brand New Choice of this month EMMYLOU HARRIS : Red Dirt Girl WPCR-19044 (WARNER) 2000 | |
|
| ||
| ●
変わらないものを守るために変わるモノ |
1947年アラバマ生まれたエミルー・ハリスは60年代終わりにグリニッジビレッジにやってきてフォーク・デュオを組んで歌いはじめる。この頃の共演者の中にはジェリー・ジェフ・ウォーカーやデヴィッド・ブロムバーグらもいた。 1971年にエミルーの才能を発見したクリス・ヒルマンはグラム・パーソンズに彼女の歌を聴きに行くようにすすめる。これがきっかけとなり、翌年エミルーはグラムのソロ・アルバムに参加。グラムが1973年に死んだ後、自分のカントリー・バンドを結成し75年にメジャーデビューを果たす。 以後、カントリー界においてそのスタイルに捕われないと同時にその歌の本質を見抜き歌い上げる才能と歌声は高く評価され続けている。 そんなイノヴェイターとしての彼女の試みが最大限に出たのが95年に発表されたアルバム『 Wrecking Ball 』である。このアルバムではU2やピーター・ゲイブリエルなどのプロデューサーと知られるダニエル・ラノワとのコラボレートで、自分を含めた既存のカントリーのスタイルを「Wrecking=破壊」するかのような挑戦的なサウンドプロダクションを提示して見せた。 その後のライブ・ツアーでもオルタナ・カントリー界でにわかに注目を集めているギタリストのバディ・ミラー、ネヴィル・ブラザーズのバックを務めた経歴を持ち、近年はダニエル・ラノワの良きパートナーとして活躍するベーシストのダリル・ジョンソン、『 Wrecking Ball 』でドラムを務めたブライアン・ブレイド(ジョニ・ミッチェルのお気に入りドラマーだ)の実の兄弟で、そのドラミングはブライアンのしなやかさとマヌ・カチェに通じる生命力の強さを感じさせるドラマー、ブレイディ・ブレイドの3人を引き連れ“SPYBOY(マルディグラの更新の中で皆の流れと反対の方へいく集団のことをこう呼ぶのだそうだ)”を名乗り『Wrecking Ball』の流れをくんだライブを敢行。同時にSPYBOY名義でのライブアルバムを発表している。 余談だが彼女のこの一連の動きはあのウィリー・ネルソンにも影響を与えたようで、ウィリーのアルバム『TEATRO』をダニエル・ラノワがプロデュース(アルバムタイトルはラノワ所有の新しいスタジオの名前でもある)、エミルーもコーラスで参加している。 今回のお題である『RED DIRT GIRL』は彼女名義のスタジオ録音としては『 Wrecki ng Ball 』から5年降りのオリジナル・アルバムにあたるわけだが、基本路線は『 W recking Ball 』の流れを組むものだと言える。 アルバムをプロデユースしているのはダニエル・ラノアの門下生として知られるマルコム・バーン(イギー・ポップやクリス・ウィートリーのアルバムをプロデュースしている経験を持つ)だが、『Wrecking Ball』でのそのサウンドメイキングの功績を評価されて今回のプロデューサー昇格となったらしい。 しかし『 Wrecking Ball 』の流れを組んではいるものの、前作と違う大きな点がひとつある。今回のアルバムに収められた楽曲は全曲エミルー・ハリス自身のペンによるものであるということだ。『 Wrecking Ball 』では全12曲の内、ソングライティングにエミルーのクレジットがあるのはわずかに2曲のみ、それも他人との共作だったのだが、エミルー自身は今回のアルバム制作について「Wrecking Ballの息子のようなアルバムにはしたくなかった。あのアルバムと競争する気はなかった。そして私がそのためにできるたったひとつの事は自分の歌を書く事だった」と語っている。 僕自身はエミルー・ハリスという人を『 Wrecking Ball 』から知った人なので(それもダニエル・ラノアが手がけていたから聴いてみようという気になった)今回の『 RED DIRT GRIL 』はどうしても『 Wrecking Ball 』と比較してどうかという目で見てしまう。そして個人的な趣味から言えば『 Wrecking Ball 』の方が好きなのも事実だ。ただ、それは僕自身がダニエル・ラノアという人の音づくりを好むからであって、単純に今回はラノアが参加していないからだけなんだと思うし、むしろ『 RED DIRT GRIL 』の方がエミルー本来のカラーが出ている肩の力の抜けた作品だと思う。 サウンドこそアンビエントのかかった正にラノア系の音ではあるけれど、その音色をとっぱらった楽曲そのものはとても味わい深いものである。おそらく生ギター1本で歌われても全く色褪せることはないだろう。音楽が“楽曲+アレンジ+演奏”の三位一体で構成されるものだとするならば『 RED DIRT GIRL 』は“楽曲8+アレンジ1+演奏1”で『 Wrecking Ball 』は“楽曲5+アレンジ3+演奏2”ぐらいの違いがあると言っていい。 『 RED DIRT GRIL 』は『 Wrecking Ball 』の続編では決してないが『 Wrecking Ball 』なくしては生まれてこなかった作品だとも言える。 彼女が『 Wrecking Ball 』で壊したかったのは、これまでの自分自身を含めたカントリーの壁だったのだと思う。“歌は世に連れ”とでも言おうか、彼女は今の世に生きる自分が感じた歌を歌いたかったのではないだろうか。それは彼女がフォーク・シンガーとして出発した頃から何も変わっていない部分だと思う。そして“今の歌”を鳴らす時に既存のカントリーのサウンドフォーマットや周囲からの「エミルーハリス=カントリーの大御所」というイメージが邪魔だったのではないか。だからそれを壊す必要があった。そこで今の彼女自身に近い歌心を持ったミュージシャン(ルシンダ・ウィリアムス、ジュリー・ミラー、スティーヴ・アール)らの曲を歌い、自分が共感するマインドを持ったミュージシャン(ニール・ヤング、ジミ・ヘンドリックス)の曲を歌い、ラノア達のサウンドを身にまとうことにした。 『 Wrecking Ball 』のサウンドを手にした彼女は、ともすれば大御所として化石化されそうなエミルー・ハリスを本来の自分の手元に引き戻すことに成功した。周囲からは革新的に見られても彼女の中ではしなければならない事をしただけの事なのだろう。そして本作『 RED DIRT GRIL 』が誕生することができたのだ。 古くからのファンは彼女の事を「裏切った」と呼ぶかも知れない。しかし、人は本来変わっていくものと変わらない部分がかならず同居するものだ。きっとエミルー自身の本来の音楽を通じて表現したいものというのは何ら変わっていない。むしろ、その変わらないものを守るために変えなければならないものもあるだという事を僕は彼女の音楽から学ぶことができたのである。 |
岩井喜昭 from " Music! Music! Music! " |
| ● 様式美を捨てたカントリーの行方 |
悔しいことに、これは素晴らしいアルバムだ。遠い島国の凡人に勝手に悔しがられる彼女もお気の毒なことだが、やっぱり悔しいものは悔しい。だって「オルタナ・カントリー」だよ、かなり眉唾もんじゃない?「カントリー」という言葉にはなんかこう、「田舎の人はみないい人だ」という幻想に基づくコンサバの居直りを感じてしまうのだ。さらに頭に「オルタナ」がつくに至っては、若者に媚びて自分達のスタイルを押しつけようとしているとしか思えない。三味線ロックとか雅楽ニューエイジとかそんな類いに聞こえるじゃないですか。 このアルバムを気に入るってことは、自分の間違いを認めること、食わず嫌いを認めることだ。なんとも悔しくお恥ずかしい次第。彼女の音楽は、カントリーの閉息した様式美なんかではなく、もちろん無理して若者に迎合するでもなく、凛とした意志に貫かれた確信的な犯行だった。 ダイナミックなパーカッションの響きは西アフリカのようでもあり、南米のようでもあり、和太鼓のようでもある。自分の耳がいかにスネアドラムに慣らされて、麻痺していたかを思い知らされる。ぶっといベース、ゴツゴツしたエレキギター、鮮烈なアコースティックギター。楽器達が作り出すどっしりとした骨格の間をうめるように漂うアンビエントなシンセサイザー。これは絶対ダニエル・ラノワの仕業だ、と思ったらちょっと違った。ラノワ一派のエンジニア、マルコム・バーンのプロデュースだそうだ。 重々しいサウンドの中を縫うエミルーのボーカルも素晴らしい。全然カントリーくさくないじゃん。出だしがちょっと掠れる歌い回しは、彼女のけなげさと真摯な想いを感じさせるし、岩山のようにそびえ立つ音空間の中でボーカルの存在感をしっかりと際立たせている。でもハスキーなのは歌い出しだけ、そのまま透明にスーっと広がって、耳にポップな後味を残すのだ。むかし書道の時間に習った「止め」と「はらい」の減り張りを思い出した。 ちょっと残念なのは、時々おおげさにヴィブラートするところか。「I Don't Wanna Talk About It Now」のナ〜ウとか。北島三郎? その筋のリスナーにとっては拍手ポイントなのかな。それと、幽霊のようなジャケット写真。音楽の芯の強さがまるで伝わってこない。このへんも文化の違いなのかなあ。まあ細かい違和感を挙げ始めたらきりがないが、なんだかんだでこのアルバムは、有無を言わさず認めざるを得ない気迫に満ちている。 例年より少し寒い東京の冬空でこのアルバムを聴く。耳に滑り込むまっすぐなメロディは、アメリカの長閑な農村地帯の風景よりも、イギリスやアイルランドのフォークソングを思い起こさせる。カントリーミュージックのルーツがイギリス・アイルランド系の移民にあることを考えれば、これはまあ当たり前な話だ。エミルーの試みは、形骸化してしまったカントリーのスピリットを取り戻して、別な進化の可能性を提示したとも言える。そういう意味では確かに「オルタナティヴ」な「カントリー」である。 でも、このアルバムの放つ静かな熱は、いちばん乗ってた頃のU2やピーター・ゲイブリエルに近い(どっちもダニエル・ラノワ絡みだし)。U2はアイルランドからアメリカに挑み、ピーターはイギリスからアフリカを眺めた。それぞれ旅の思惑は違えども、結局辿り着いたシーンは異文化同士の「出会い直し」だったのかも知れない。 |
山下元裕 from " FLIP SIDE of the moon " |
| ● 面白いサウンドなのだが... |
となり町、東京・大森においしいと評判のカレー屋があり、映画を観に行った帰りに寄ってみた。細長い店の二階にあがり、ふと壁を見ると音を消したTVがついている。映っているのはスカパーで、番組は海外の音楽賞の中継。こりゃしめた、肝心の音楽が聴けないのはナンだけど、まぁ誰がどんな賞を貰っているか観ていよう。 数分後、「...??」。数々の賞が授けられているが、受賞者の名前をひとりも知らないのだ。会場は巨大、観客席は満員。それなりに権威のある賞なのだろうに、となりの宇宙の音楽賞か?これは一体ななんだ?そして紹介されたヴィデオ・クリップに登場したのは、ヒゲにテンガロン・ハットのオトッツァン。あ、これってカントリー・ミュージック・アワードだったのか。 「となりの宇宙」の最も新しい音が、今月紹介のエミルー・ハリスである。しかし、これ、カントリーなのだろうか。曲によってはほとんどオルタナだよ。というか、要するにロック。私などがイメージするアメリカン・ロックそのものという感じがする。 肝心のロック・シーンがダンス・ミュージックやら、ラップやらに席捲されてしまい、ドラムにギターにベースとヴォーカルみたいな典型的なロックはどこに行ったのかと思ったら、ここにいた。へぇ、カントリー・ミュージック・シーンってこうなっていたのか。 誤解を恐れずに書けば、なんか、ムーンライダーズのようでもあり、'80年代末『Beauty』の頃の坂本龍一のようでもある。ギターの入り方などがそっくりなのだ。ムーンライダーズの根っこにはかなり強固にカントリーが居すわっていると思うが、坂本とカントリーは、ううむ、最も対照的なような、通じるところもあるような...。 声もいい。この声質は好きな感じだ。発声も適度にルーズで、ロックらしい心地良さに溢れている。曲まぁまぁ、アレンジ良し、声良し、発声良しとなれば、言うことなしのようだが...ちょっと気になるところもあった。ある曲のエンディングで軍隊のラッパを思わせるハミングがあったのだ。 気になって歌詞を読んでみると、これが微妙。案の定、軍人墓地に眠る父親を歌ったものだったのだが、戦争賛美のような、反戦歌のような...靖国モンダイのような歌なのだ。英語の原文にも目を通したが、右か左か、その微妙なニュアンスはわからなかった。どっちなんだろう? もしもこれが右ならば、即座にこのアルバムはノーだ。このCDをプレイする直前、ついさっきまではブラジルの鬼才、カエターノ・ヴェローゾのCDを聴いていた。カエターノはかつてブラジルの軍事政権に反旗を翻して投獄され、国外追放のような形でイギリスに亡命を余儀なくされた人物である。カエターノはどうにか生きながらえたが、他の南米諸国では「国民に与える影響が大きい」として命を断たれた者、両手を潰されたギタリストなどもいる。そこまでして、庶民の側、自由の側に立つべき大衆音楽が、軍事にコミットしても良いのだろうか? なんか、異常に難しくなってしまったので、ここまで。ほんと、ニュアンス的にはどっちなんでしょうね。彼女のようなオルタナ・カントリーは、凝ったアレンジと最先端の音色で若いファン層も着実に増やしているらしい。でも、それで内容がコンサバだったらばちょっと困るな。サウンドに騙されてヘンな指向が身についてしまう。むしろダサダサのカントリーならば、明らかに若い連中は聴かないから「安全」なんだけれどね。もうちょっと英語の勉強して、再研究してみます。となりの宇宙のことば、ちょっと難しいや。 |
定成寛 from " サダナリ・デラックス " |
See you next month
来月は " Good Oid Choice " 名盤の月です
(C) Written and desined by the Rock Crusaders 1998-2001
Japan
| Back to the | Index page |