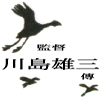 |
99/06/11 監督 川島雄三傳 その生涯 |
| 川島その死 死に至る病、だったのか? |
|
|
| 東京・芝 日活アパートの記 |
| その死について記す。死の時は昭和38年6月11日未明。死亡推定時刻は午前5時である。場所は東京都港区芝公園13番地日活アパート9階。死因は両側性肺気腫を原因とする「肺性心」−心臓の衰弱であった。 前夜は銀座のバー「エスポワール」を訪れ午前零時過ぎに酔って帰宅、直ぐには眠らずに布団にうつ伏せになって本を読んでいたようだ。枕許には座談会で東宝の体制批判をしてしまい、その発表を気に病んでいたという『中央公論』昭和38年7月号と、撮影予定だった『寛政太陽傳』−写楽の資料となる『江戸商売図絵』(三谷一馬・編)が広げられた儘だった、しかもそれらを読んでいる姿勢での死だったという。 内縁の妻、八重司さんとは数年前から寝室を異にしていたので、気づかれることのないひとりきりの死であったとか、この頃銀座のあるホステスの部屋に泊まる事が多く、この晩は久々に自宅へ帰っての就寝であった等々の逸話もあるが、前者はともかく後者は本筋とは関係のないことだ。 明けて11日午前、死因の特定のために大塚の東京監察医務院に移送され、検死を行ったのち芝の浄雲院へ。同日午後密葬。雨の中午後3時に出棺、遺体のまわりには好物のさくらんぼが撒き散らされていた。桐ヶ谷斎場で荼毘に伏されて、ここで一旦自宅に還っている。本葬は15日、その模様を納めたの8mmには、フランキー堺、三橋達也を筆頭に桂小金治、新珠三千代、若尾文子、香川京子、星由里子らの姿があった。そして八重司夫人の胸に抱かれ故郷下北の恐山に還った。 |
![]()
| まず大前提について考えたい。川島の死は件の遺伝障害に因るもので、先天的、運命的なものであったのか否かということについて。 現時点での私の考えは、イエスでもありノーでもある。その比率は50%ずつといったところか。例えばここに脚本家・猪俣勝人氏の著書『日本映画名作全史・戦後編』(社会思想社)があるが、これには「筋肉がしだいになえてゆく奇病にとりつかて、死んだ」とある。この文章からは筋肉が萎えて、病床で、衰弱して死んだかの様に思われる。そしてこれが川島に対する一般的な(?)記述でもある。 ところが実際は全く異なる。最後の夜−昭和38年6月10日もいつもの様に銀座で呑んでいた。撮影も直前まで行っており、遺作となった『イチかバチか』が封切られたのは実に死の5日後である。しかも死因は心臓の衰弱。これは一体どう結論付けられるのだろうか。 遺伝障害としての筋萎縮症は基礎体力と抵抗力を奪い、それに毎日のアルコールと睡眠不足が追い打ちをかけたのではないだろうか。連日の飲酒や深夜迄のハードワークで突然死、過労死をしてしまう者は健常者でもいる。そんな生活をあのか細い体で続けていたならば、心臓への悪影響は計り知れないものがある。 そして、次が問題なのだ。確かに体は弱かった。だが実は、もっとその体をいたわれば、生き長らえたのではにないかとも思われるのだ。驚くべき発言に川島の検死をした監察医の言葉「心臓に幾分かの弱さはあったが内臓は健全、いたわっていれば相当長生きをする身体でしたが...」がある。 もしもその検死に私が立ち会っていたならば、驚きのあまり大声をあげていたかもしれない。「余命幾許(いくばく)もない体ではなかったんですか?!」と。どうやらそうではないいらしいのだ。 脚本家・柳沢類寿の文章が興味深い。「川島は彼の作品に好んで登場した、少しそそっかしい性格の人物のように、彼は自分自身の人生を演出していた」のではないかというのだ。私も同感である。「私ニハ時間ガアリマセン」と自らの短命を早々に結論付けて、破滅的に振る舞い、それによって自らの命を縮めてしまったということはないだろうか。 私にはこの様な意味で、「この人は生きいそぎの人であった」と思う。粗忽者は数知れないが、自らの命迄も縮めてしまったかもしれない人というのは、珍しい。 さらにこの川島の人生観が、川島の作風を、あの映画たちの雰囲気を作っている様にも思う。とんでもない勘違いという喜劇と、死という悲劇、その共存というあの儚き雰囲気を...。 |
![]()
| そしてこの死は映画界にとって、監督川島雄三にとってはどの様な意味があったのだろうか。それについては現在じっくりと考えているところである。 川島の死後に撮られた幾つかの映画、幾つかの風潮を考えてみる。例えばアクション、任侠物、バイオレンス、ポルノ、アングラから異常性愛物まで...高度成長期の終焉と共によりダイレクトな映像表現へと向かっていった昭和40年代の日本映画界を、50代を迎え円熟期にさしかからんとする川島はどの様に生き抜いていったのだろうか。そして、川島のあと5本、あと10本の作品は、他の映画人、ひいては日本映画界にどの様な影響を与え得たのであろうか。 それにしても、あのあと、どんな作品を撮ったのだろう。増村保造路線では強烈過ぎると思うし、今村昌平は近いようで遠い。市川崑も微妙なところである。川島的スラップスティックを継承しようと必死にもがいていたのが、松竹の後輩、前田陽一。もう一歩進んで、それなりに継承していた、いや唯一の後継者と言えるのが明大、東宝の後輩である鬼才・岡本喜八ではないだろうか。 そして意外にも劇映画時代の西村昭五郎あたりが一番近いのかもしれない。あのような硬質な、鬼気せまる現代劇を残して呉れたのではないだろうか。この件については後日、ゆっくり記す。 |
![]()
| 死についての記述の中で、印象深いものが幾つかある。生前の川島に最後に会ったのは脚本家の笠原良三氏と、『雁の寺』『しとやかな獣』で企画を担当した大映の三熊将暉氏であった。銀座のバー「エスポワール」で川島に出会った両氏は、その雰囲気の違いに驚く。あまりにも元気がなく、一点を見つめるかのごとく虚ろであったと記す笠原氏、出来上がってもいなければ絡んでも来ず、おとなしくて真面目な顔さえしていたと記す三熊氏。そして偶然触れた川島の膝が驚く程に冷たかったというのだ。「その時既に生死の間をさまよっていたのではないかと思えたりして物悲しかった」−三熊氏の、この言葉が忘れられない。 柳沢類寿が描写した輸送車の中の様子も印象的である。息を引き取った東京・芝公園の日活アパートから、監察医務院へと移送する車には柳沢と今村昌平が同乗した。そこでの今村の言葉「死んだ事を...川島さんはまだ、気が付いて居ないようですナ」も忘れ難きものである。いつものように口を尖らしたその死に顔は、まさにその言葉の様だったらしい。読売新聞の映画記者・谷村錦一氏はその表情を「何しに来たの、ああ、僕は死んでいるのかい」とでも言いそうだったと書いている。 更に松竹の先輩、渋谷実監督は「肉体の死、精神の死」という言葉を記している。川島の死は肉体と精神の「分断」であって、消滅は意味していないというのだ。 この言葉には強く共感する。あまりにも突然の、本人も意識することもなかったであろう死は、あくまで肉体に対するものであり、その精神は今でも、1999年の東京のどこかにぽっかりと浮かんで、彷徨っているのではないかと考えているからだ。 |

| 「今でも川島を見る」という人がいる。作家の童門冬二氏である。川島とは昭和30年頃に渋谷のとんかつ屋「とん平」で出会い、その強烈過ぎる印象に取り憑かれている。すっかり街並みの変わった渋谷だが、今でも"のんべい横町"の共同便所の影から川島が現れて、酔って絡んで来た時のセリフ「そも、おぬし、何者?」と問いかけてくるという。 つい先日、平成11年5月に発表したコラムにそのように記していたのだ。松尾芭蕉の俳風「不易流行」−かわるものとかわらないのの一体化、見えないものを見る芸術的次元−の精神である。 この気持ちは本当に良く判る。この特集を立ち上げんと川島を辿ること数カ月。ある日私は「川島は故人である」ということを忘れている自分に気が付いた。毎日関連の資料を読み、ビデオを観て、ロケ地を歩く...そんなことをしている間に川島雄三というのは現役の監督で、今でも銀座のバーや渋谷のとんかつ屋で悪い酒を煽り、オダをあげているかの如く錯覚してしまったのだ。 渋谷は自宅が近いので良く飲みに行く。銀座は会社が近いのでこれまた良く飲みに行く。もしも街角で川島に出逢い、「そも、おぬし、何者?」と問い詰められたら...「貴方のファンです」と答えればいいのか。それとももっと、捻った答えをすべきなのか...。 全く唐突な、悲劇的な死に方をした川島だが、逆にその唐突さゆえに肉体は失われても、精神は残り、川島を追う者、語るも者の傍に永久に生き続ける...死を美化する事を嫌い、宗教やオカルトも信じない私だが、ついこんなことを考えてもしまうのだ。 |
 |
監督・川島雄三傳 目次に戻る | ||